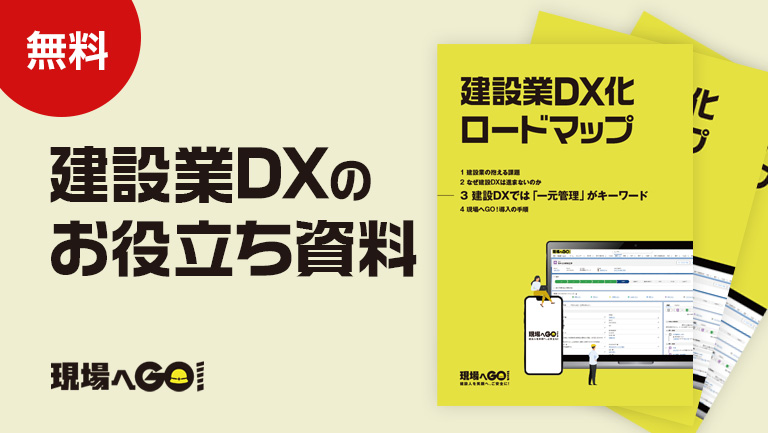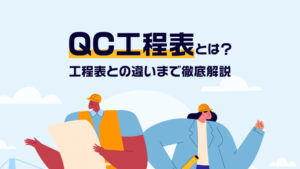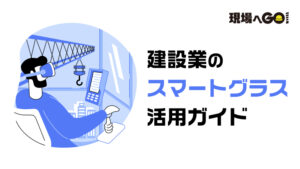ICT施工とは?建設業での活用方法を解説!

【はじめに】建設業で広がるICT活用の流れ

建設業界ではいま、これまでにないスピードでデジタル化が進んでいます。背景にはいくつかの要因があります。まず一つ目は、少子高齢化による担い手不足です。若い人材がなかなか集まらない一方で、熟練技術者の高齢化が進み、現場の人手は年々限られてきています。
二つ目は、生産性の課題です。建設業は「人の手」に頼る部分が大きく、他産業に比べて労働生産性が低いと言われてきました。長時間労働が常態化しやすいこともあり、働き方改革への対応も求められています。
こうした課題を解決するために注目されているのが、ICT(情報通信技術)の活用です。ドローンや3Dスキャナ、クラウドシステムやAIなどを取り入れることで、従来のやり方では時間や人手がかかっていた作業を効率化し、より少ない人数でも質の高い施工を実現できるようになってきました。
単なる「最新技術の導入」ではなく、業界全体の構造を変える可能性を秘めた取り組みとして、ICT施工が広がりつつあるのです。
ICT施工とは?
ICT(情報通信技術)を活用した建設プロセスの効率化
ICT施工とは、その名の通り 情報通信技術(ICT: Information and Communication Technology)を建設現場に取り入れる取り組み のことです。従来の建設プロセスは「測量 → 設計 → 施工 → 管理」と段階ごとに進められてきましたが、それぞれの工程が紙や2次元図面を介して分断されることが多く、情報の引き継ぎに時間や労力がかかっていました。
そこで登場したのが、ICTを活用した施工手法です。たとえばドローンによる空撮で地形を3Dデータ化すれば、従来数日かかっていた測量がわずか数時間で完了します。また、BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)といった3次元モデルを使えば、設計データをそのまま施工や維持管理に活かすことができ、情報の重複入力やミスを減らすことが可能になります。
つまりICT施工は、「現場の勘と経験に頼っていた作業をデータでつなぎ直し、効率と精度を同時に高める仕組み」と言えます。
国土交通省の「i-Construction」とICT施工の関係
日本でICT施工が一気に広がった背景には、国土交通省が進める 「i-Construction(アイ・コンストラクション)」 があります。これは建設現場の生産性を抜本的に高めるために掲げられた施策で、2016年から本格的に導入が始まりました。
i-Constructionでは特に「3次元データの活用」を重視しており、測量から設計、施工、維持管理までをデジタルデータで一貫管理することを推奨しています。その中心にあるのがICT施工であり、ドローン測量やICT建機の導入はその代表的な例です。
つまり、ICT施工は単なる技術トレンドではなく、国の方針として推進されている建設業界の変革でもあります。今後は公共工事だけでなく民間工事でも、こうしたICTを前提とした施工が一般的になっていくと考えられます。
ICT施工の主な活用分野

測量(ドローン・レーザースキャナ)
従来の測量は、測量士が現場を歩き回りながらポイントごとにデータを取得する手法が中心でした。山間部や広大な工事現場では多くの人員と時間が必要で、安全面のリスクも伴います。
ICT施工では ドローンによる空撮やレーザースキャナによる3D測量 が活用され、短時間で広範囲の地形データを取得できるようになりました。これにより、正確な3次元地形モデルを作成し、設計や施工の初期段階からデータを有効に使うことが可能になっています。
設計(BIM・CIMによる3次元モデル活用)
設計段階では、BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling) が導入され始めています。これらは建物やインフラを「3次元モデル」として可視化し、部材の寸法、位置、工程、コストなどの情報を統合して管理できる仕組みです。
従来の2次元図面では見落としがちな干渉や設計ミスを、事前に3Dモデルで確認できるため、後工程での手戻りを大幅に減らす効果があります。また、発注者や施工会社との意思疎通もスムーズになり、プロジェクト全体の透明性が高まります。
施工(ICT建機・自動化施工)
施工現場では、ICT建機 の活用が進んでいます。たとえばブルドーザーや油圧ショベルに3次元設計データを読み込ませ、GPSやセンサーで位置を自動制御することで、オペレーターの熟練度に左右されにくい精度の高い施工が可能になります。
また、半自動・自動運転による施工は作業効率を上げるだけでなく、人手不足の解消や安全性の向上にもつながります。将来的にはAIと組み合わせた完全自動化施工も期待されています。
管理(IoT・クラウド・遠隔監視)
工事の進捗や品質管理の面でも、ICTは大きな役割を果たします。IoTセンサーやクラウドシステム を活用すれば、現場の機械の稼働状況や資材の在庫、労働環境(温度・湿度など)をリアルタイムで把握できます。
また、遠隔カメラやウェアラブルデバイスを使うことで、現場にいなくても安全管理や進捗確認が可能になり、本社や発注者と情報を共有しながら施工を進めることができます。こうした取り組みは、コスト削減や効率化だけでなく、安全で持続可能な働き方の実現にもつながっています。
BIM・CIMとICT施工の関係性
設計から施工・維持管理までをつなぐ3次元データの役割
ICT施工の大きな特徴の一つが、設計から維持管理までを一貫してデータでつなぐことです。その中心にあるのが BIM(Building Information Modeling)とCIM(Construction Information Modeling) です。
BIMは主に建築物を対象とし、CIMは道路や橋、ダムといった土木構造物を対象にしていますが、いずれも「3次元モデルに必要な情報を付与して、建設プロセス全体で活用する」点で共通しています。
例えば設計段階で作成した3Dモデルは、施工時にはICT建機に取り込むことで自動制御に活用できますし、竣工後は維持管理のデータベースとして活かすことが可能です。これにより、従来は分断されていた「設計図面」「施工データ」「維持管理記録」が一つの情報基盤でつながり、建設ライフサイクル全体を通じた効率化が実現します。
ICT施工の中核技術としての位置づけ
ICT施工の分野にはドローンやIoT、クラウド管理などさまざまな技術がありますが、その中でも BIM・CIMは「情報のハブ」として中核を担う存在 です。
なぜなら、すべての工程で扱う情報のベースとなるのが「設計データ」であり、そのデータを3次元かつ統合的に扱える仕組みがBIM/CIMだからです。
国土交通省の「i-Construction」でも、BIM/CIMの活用は重点的に推進されています。ICT施工がただの作業効率化で終わらず、建設業全体のデジタル変革につながっているのは、この3次元データ活用が大きな役割を果たしているからと言えるでしょう。
ICT施工のメリット

生産性向上と工期短縮
ICT施工の最大のメリットは、作業の効率化による生産性向上です。ドローンによる測量は、従来なら数日かかった作業をわずか数時間で終わらせることができます。また、ICT建機を使えば、オペレーターが細かく操作しなくても自動で高精度な施工が可能になり、工期の短縮につながります。
人手不足が深刻化する中で、少人数でも従来と同等、あるいはそれ以上の成果を上げられる点は大きな強みです。
品質と安全性の確保
ICT施工では、3次元データを基盤に作業を進めるため、設計通りの精度で施工できる という利点があります。従来のように「人の感覚」に頼る部分が減り、仕上がりのばらつきが少なくなります。
さらに、現場での危険な作業をドローンや自動建機に置き換えることで、作業員が高所や重機周辺に立ち入る必要が減り、安全性の向上にも直結します。これは労働災害のリスク低減という観点からも重要です。
コスト削減と効率的な管理
一見するとICT施工は高額なシステムや機材が必要に思えますが、長期的にはコスト削減効果が期待できます。作業の効率化によって人件費や工期が削減されるだけでなく、設計ミスや施工不良による手戻りを防ぐことで無駄なコストを抑えられます。
また、IoTやクラウドを活用すれば、現場の進捗や資材管理をリアルタイムで共有できるため、現場と本社、発注者の間で情報の食い違いが起こりにくくなります。結果として、プロジェクト全体のマネジメントがスムーズに進み、無駄のない運営が可能になります。
ICT施工の課題と今後の展望
導入コストや教育のハードル
ICT施工は大きなメリットをもたらす一方で、初期投資の大きさが課題として挙げられます。ドローンやICT建機、3次元モデリングソフトなどは高額で、中小規模の建設会社にとっては導入のハードルが高いのが実情です。
また、機材を導入しても、現場で活用するためにはICTに精通した人材の育成が不可欠です。従来の施工方法しか経験のない技術者が多い中で、新しいツールを現場に定着させるには時間と教育コストがかかります。
システム間の互換性・データ共有の問題
ICT施工を進めるうえで、システムやソフト間のデータ互換性も課題になります。BIM/CIMの3次元データを施工段階や維持管理に引き継ぐ際、フォーマットが異なるためにデータ変換が必要になったり、情報の一部が失われてしまうケースも少なくありません。
さらに、発注者・設計者・施工者・管理者と多くの関係者が関わる建設業では、データ共有のルール作りが不可欠です。誰がどの情報をどこまで扱えるのか、セキュリティや責任分担を明確にすることも今後の大きなテーマとなります。
今後期待される自動化・AIとの連携
今後の展望として注目されているのが、自動化とAIの活用です。ICT建機の自動運転や、ドローンによる自動測量はすでに実用化が進んでいますが、将来的にはAIが施工データを解析し、最適な工法やスケジュールを提案する仕組みも考えられています。
また、維持管理の分野では、構造物の劣化状況をセンサーが自動検知し、AIが修繕時期を予測するといった仕組みも広がるでしょう。これにより、人手不足を補いながら、より安全で効率的な建設・管理が実現すると期待されています。
【まとめ】ICT施工がもたらす建設業の未来

ICT施工を理解する人材が必要
ICT施工は、単なる最新技術の導入にとどまらず、建設業そのもののあり方を変えつつあります。測量や設計、施工、管理といった各工程をデータでつなぐことで、作業の効率化や品質の安定、安全性の向上が実現され、業界全体の生産性革命へとつながっています。
こうしたデジタル技術の活用は、労働時間の削減や業務の標準化にも寄与し、働き方改革の一環としても期待されています。これまで「人の経験」に大きく依存してきた建設現場が、データとテクノロジーを駆使することで、より持続可能で魅力ある職場へと進化していくでしょう。
ただし、その変化を支えるのはやはり「現場の人材」です。ICT施工を真に活かすためには、技術を理解し活用できる人材の育成が欠かせません。そうした課題に向き合いながらも、業界全体で取り組むべき方向性は明らかです。
現場へGO!のご紹介
「現場へGO!」は、建設業向けに設計された統合型アプリケーションです。階層型の見積もりやグラフィカルな工程表など、現場で必要な情報を一つのシステムで管理できるようになっています。
ICT施工で得られたデータと組み合わせることで、現場の進捗や資材管理、工程調整をスムーズに行えるため、現場の効率化をさらに後押しします。施工のデジタル化と合わせて使うことで、建設現場全体の作業がより計画的で見通しの良いものになるでしょう。