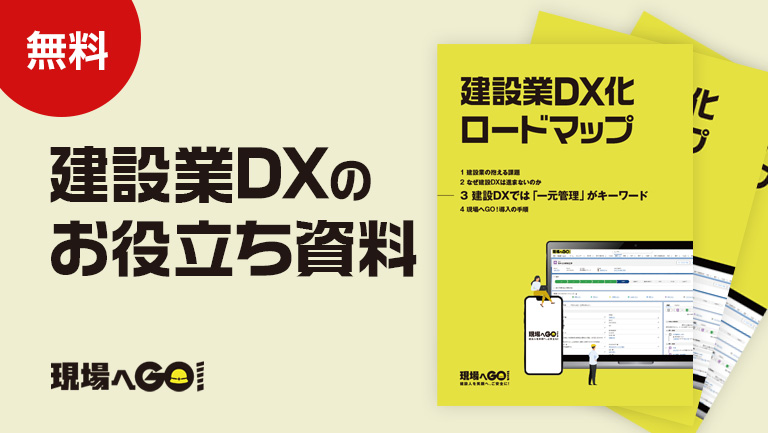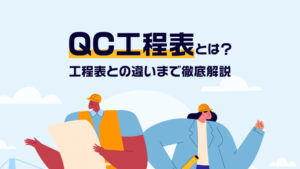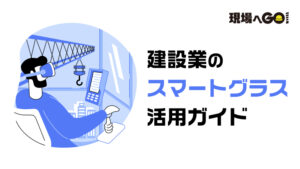建設業でも義務化!?アルコールチェックについて解説!

【はじめに】なぜ建設業でアルコールチェックが必須になったのか

労働災害・交通事故の背景
建設業は他の産業と比べても労働災害の発生率が高い業界です。特に、ダンプカーやトラックによる道路事故、フォークリフトや重機による構内事故は、毎年一定数発生しています。
国土交通省や厚生労働省の統計を見ても、死亡災害の大きな割合を占めているのが「車両系の事故」です。
飲酒による判断力の低下や反応の遅れは、建設現場において致命的なリスクにつながります。例えば、フォークリフトでの荷役作業中にわずかな判断の遅れがあれば、資材の転倒や挟まれ事故を招きかねません。さらに、建設業では夜間工事や残業明けの早朝運転など、不規則な勤務形態が多く、飲酒と疲労が重なることで事故リスクは一層高まります。
こうした背景から、「建設業こそアルコールチェックの徹底が必要」との認識が強まってきました。
法改正による建設業への影響
アルコールチェックの義務化は、もともと運送業界(緑ナンバー車両)から始まりました。しかし、2022年4月の道路交通法施行規則の改正により、白ナンバー車両を使用する事業者にも義務が拡大されました。
建設業でも、以下のような事業所が対象となっています。
- ダンプカーやトラックを5台以上保有している事業所
- 乗車定員11人以上の車両を1台でも保有している事業所
2023年12月からはアルコール検知器の使用が完全に義務化され、現在では「運転前後のチェック」「記録の保存」「検知器の管理」が必須となっています。
建設業は、トラックやダンプカーでの資材運搬、フォークリフトによる倉庫内作業など、日常的に車両を使用する業界です。そのため、法改正は単なる「形式的な対応」ではなく、現場の安全確保そのものに直結する課題となっています。
アルコールチェック制度の流れ
アルコールチェック制度はここ数年で大きく変化してきました。とくに建設業界にとっては、車両の種類や現場環境が多様なだけに、制度の動きを正しく理解しておくことが欠かせません。ここでは、2022年から2025年までの流れを年表形式で整理します。
【2022年】白ナンバー車への義務化(目視チェック)
2022年4月の道路交通法施行規則の改正により、これまで「緑ナンバー車(運送業)」だけが対象だったアルコールチェックの義務が、白ナンバー車を使用する事業者にも拡大されました。
建設会社で言えば、資材を運搬するダンプカーや社用トラックがこれに該当します。
この段階では、運転前後に「安全運転管理者がドライバーの酒気帯びの有無を目視で確認する」ことが求められました。
【2023年】アルコール検知器使用の完全義務化
翌2023年12月からは、単なる目視確認にとどまらず、アルコール検知器を用いたチェックが完全に義務化されました。
さらに、
- チェック結果の記録を保存する(1年以上)
- 検知器そのものの精度や管理体制を維持する
といった細かなルールも整備され、形式的なチェックではなく「証拠として残す仕組み」が必要になっています。
この段階で多くの建設会社が「直行直帰の社員をどう管理するか」「現場ごとに検知器を配置すべきか」といった課題に直面しました。
【2025年】建設業に求められる最新対応ポイント
2025年は、制度そのものに大きな追加改正は予定されていませんが、建設業界においては実効性ある運用が一層強く求められる年になると考えられます。
具体的には下記のような事がカギになります。
- ICT・クラウドシステムの活用による遠隔チェックの導入
- フォークリフトやクレーンなど「道路外で使う車両」への安全教育の強化
- 下請け業者も含めたグループ全体での運用ルール整備
つまり、2025年は「法律に従うだけ」から一歩進み、自社のリスクに即したアルコールチェック体制をどう構築するかが問われる時代だと言えるでしょう。
義務対象の明確化、建設業の車両はどこまで対象になるのか?

アルコールチェック制度は「すべての車両に義務がある」と誤解されがちですが、実際には道路を走るかどうかが大きな判断基準になります。建設業でよく使われる車両を例にとって整理してみましょう。
ダンプカー、社用トラックなど道路走行する車両
まず確実に対象となるのは、道路を走行する車両です。
たとえば、資材を運搬するダンプカーや、現場間を移動する社用トラックは、白ナンバーであってもアルコールチェックの義務が課されます。
また、建設業では工事現場が点在しており「短時間の移動だから大丈夫だろう」と見落とされがちですが、たとえ数キロの移動であっても道路を走行する以上は義務対象になります。
フォークリフト・クレーン車・ユンボなど構内専用車両の扱い
一方で、フォークリフトやクレーン車、ユンボ(油圧ショベル)など、構内専用で使われる建設機械は、法律上のアルコールチェック義務の対象外とされています。
ただし注意が必要なのは、これらの車両であっても「公道を横断する」「現場間を道路経由で移動する」といったケースでは対象になることです。
実際に「フォークリフトで敷地内から隣接する現場に資材を運ぶために道路を横断していた」という事例で、道路交通法上の適用を受けたケースもあります。
「対象車両」と「対象外車両」の誤解しやすい境界線
誤解が多いのは、「フォークリフトや重機は構内作業用だからアルコールチェックは不要」と一律に判断してしまうことです。
実際には、運用状況によって対象にも対象外にもなり得るため、次のような点を整理しておく必要があります。
- ダンプカーや社用トラック → 常に対象
- フォークリフトやユンボ → 原則対象外だが、公道を走れば対象
- クレーン車 → 車両区分によっては道路交通法の適用を受ける場合あり
この境界をあいまいにしてしまうと、知らないうちに法令違反となるリスクがあります。
したがって、自社で保有しているすべての車両について、「道路を走行するかどうか」を基準に区分し、運用ルールを明確にすることが重要です。
建設業特有の課題とリスク
アルコールチェック制度は業種を問わず義務化されていますが、建設業には特有の働き方や現場環境があり、他産業以上に運用の難しさがあります。ここでは、建設業ならではの課題とリスクを整理してみましょう。
直行直帰・遠隔現場でのチェック体制の難しさ
建設業では、社員が毎日同じ事務所から出発するとは限りません。
「自宅から現場に直行」「現場から直接帰宅」といった働き方が多いため、安全運転管理者によるアルコールチェックをどう実施するかが大きな課題となります。
例えば、郊外の現場や地方の工事現場では、本社から担当者を派遣して目視確認するのは現実的ではありません。こうした場合には、クラウド対応のアルコール検知器や、スマートフォンと連動したリモートチェックが必要になります。
夜間工事・長時間労働と飲酒リスク
建設業では、交通量が少ない時間帯に行われる夜間工事が少なくありません。
また、工期に追われる現場では、日中から深夜まで長時間労働が発生するケースもあります。
このような環境では、勤務終了後の「ちょっと一杯」が翌日の早朝勤務に影響を及ぼすことがあり、いわゆる「残酒運転」のリスクが高まります。
とくに夏場のビールや冬場の宴会シーズンなど、飲酒量が増えるタイミングでは、アルコールが完全に抜けきらないまま運転してしまう事例が後を絶ちません。
フォークリフト・重機による現場内事故の事例
アルコールチェック義務の対象外とされることが多いフォークリフトや重機ですが、建設現場での事故件数は決して少なくありません。
例えば、フォークリフトの操作ミスによる資材の転倒事故や、バック時に作業員を巻き込む事故は毎年発生しています。
仮に飲酒が直接の原因でなくても、アルコールによる集中力の低下が事故リスクを高める可能性は否定できません。
そのため、多くの建設会社では「道路を走らない車両であっても、自主的にアルコールチェックを実施する」という取り組みを進めています。
【2025年版】アルコールチェックの具体的な義務内容

2025年現在、建設業を含む事業者にはアルコールチェックの実施が強く求められています。ここでは、実際にどのような義務があるのかを整理してみましょう。
運転前後の検知器チェックと目視確認
すべての対象車両について、運転の前後にアルコールチェックを行うことが義務づけられています。
具体的には、
- アルコール検知器を用いて数値を確認する
- 併せて安全運転管理者や上長が目視で顔色や言動を確認する
という二段構えが基本です。
単に「機械で測ったから大丈夫」ではなく、人の目によるチェックを組み合わせることが制度の狙いです。
記録の1年間以上保存が義務化
アルコールチェックの結果は、1年以上保存することが義務化されています。
紙の台帳に記録する方法でも構いませんが、最近はクラウド型システムを利用してデータを自動保存するケースが増えています。
建設会社の場合、複数現場に社員が散らばっているため、紙での管理では抜け漏れが発生しやすいのが実情です。
そのため、本社から一元的に管理できる仕組みを導入することが望ましいでしょう。
検知器の管理・点検体制
アルコール検知器は、ただ置いておくだけでは義務を果たしたことになりません。
制度では、常に正確な測定ができるように管理・点検することが求められています。
例えば、
- 定期的に校正(精度確認)を行う
- 故障や不具合を見つけたらすぐ交換する
- 誰がどの機器を使ったかを把握する
といった運用が必要です。
建設現場では粉じんや湿気で機器が故障しやすいため、現場環境に合った耐久性のある機器を選ぶことも大切なポイントです。
違反時のリスクと責任
アルコールチェックの義務は「努力目標」ではなく、事業者に課せられた明確なルールです。万が一これを怠った場合、単なる形式的な違反にとどまらず、会社全体に大きなリスクをもたらします。
行政処分・業務停止命令の可能性
アルコールチェックを実施していない、あるいは記録を保存していないことが発覚した場合、警察や運輸局からの指導・行政処分の対象になることがあります。
特に、飲酒運転に関連する事故が発生した場合には、車両の使用停止や業務停止命令に至るケースもあり、現場の稼働に直結する深刻な問題となります。
事故発生時の安全運転管理者や会社の法的責任
アルコールチェックを怠った状態で事故が起きた場合、安全運転管理者個人の責任や、会社としての法的責任が問われます。
過失が認められれば、損害賠償や刑事責任につながる可能性も否定できません。
たとえば、飲酒が疑われる運転者を「見て見ぬふり」で現場に送り出した場合、管理者が安全配慮義務を果たしていないと判断される恐れがあります。
社会的信用・入札参加資格への影響
建設業では「信用」が何よりも重要です。
アルコールチェックの不備や飲酒運転事故が公になれば、元請けや取引先からの信頼を失い、公共工事の入札参加資格に影響する可能性も出てきます。
近年は、発注者が安全管理体制を重視する傾向が強まっており、「アルコールチェックを徹底しているかどうか」も評価基準の一つになりつつあります。
つまり、制度遵守は単なる法令対応ではなく、会社の競争力を守るための条件といえるでしょう。
建設業特有の対応ポイントと方策

建設業におけるアルコールチェックは、一般のオフィス業務とは異なり「直行直帰」「遠隔地の現場」「夜間作業」など特有の環境で運用されるのが特徴です。そのため、制度を形だけ守るのではなく、現場に即した仕組み作りが欠かせません。
モバイル検知器の活用と「対面に準ずる方法」の導入
直行直帰が多い建設業では、毎回社員が営業所に立ち寄ってチェックを受けるのは現実的ではありません。
そこで注目されているのが、モバイル型のアルコール検知器と、スマートフォンのカメラや通話を組み合わせた「対面に準ずる方法」です。
「Bqey(ビーキー)」や「スリーゼロ」など、クラウドに測定結果を送信して本人確認まで行えるサービスはいくつか存在しますが、中でも建設業におすすめなのが「セーフくん」です。セーフくんはアルコールチェックの結果と本人確認を同時に記録できるだけでなく、Salesforceプラットフォームの上で動くアプリなのでデータを一元管理できる点が大きな特徴です。これにより、本社から遠隔現場の状況をリアルタイムで把握でき、形式的ではなく実効性のある運用が可能になります。
デジタル記録・クラウド保存による業務効率化
紙の台帳で記録を残す方法はシンプルですが、現場が複数に分かれている建設業では、提出漏れや保管ミスのリスクが高まります。
クラウド型の管理システムを導入すれば、自動で記録を保存・一元管理でき、監査や行政からの確認にもスムーズに対応できます。
さらに、各現場の状況をリアルタイムで把握できるため、安全運転管理者の負担軽減にもつながります。
安全運転管理者の教育・社内ルールの明文化
制度を守るうえで忘れてはならないのが「人の意識づけ」です。
どんなに検知器やシステムを整えても、現場での運用が徹底されなければ意味がありません。
- 安全運転管理者への定期的な教育
- アルコールチェックの実施手順や違反時の対応を明文化した社内ルール
- 全社員に対する周知・研修
こうした取り組みを積み重ねることで、制度が「形だけの義務」ではなく、現場の安全文化として根付くことになります。
2025年度に向けたステップアップロードマップ
アルコールチェック制度はすでに義務化されていますが、建設業界では「やってはいるが本当に十分か?」と不安を抱えている会社も少なくありません。ここでは、2025年度に向けて体制をより強固にするためのステップアップの流れを整理します。
現行体制の棚卸し
まず必要なのは、自社が今どのレベルで対応できているかの棚卸しです。
「検知器は全員に行き渡っているか」「記録保存は紙とデジタルどちらで管理しているか」「直行直帰の社員にも対応できているか」など、現状を見える化することが出発点となります。
車両・現場ごとのリスク評価
次に取り組みたいのは、車両や現場ごとのリスク分析です。
ダンプカーやトラックのように道路を走る車両はもちろん、フォークリフトやクレーンといった構内専用車両も、事故が起これば大きな被害につながります。
現場の規模や勤務形態、夜間工事の有無などを踏まえ、「どこに最もリスクが集中しているか」を把握することが、安全対策の優先順位を決めるカギとなります。
検知器導入・管理システムの活用
リスクを洗い出したうえで、モバイル型検知器やクラウド管理システムの導入を検討します。
特に、複数現場を抱える建設業では「本社で一括管理できる仕組み」が効果的です。
システムを活用すれば、管理者が紙の台帳を逐一チェックする手間も減り、不正防止と業務効率化を同時に実現できます。
継続的改善と安全文化の醸成
最後に大切なのは、制度を「やらされている義務」から「当たり前の安全文化」へと根付かせることです。
定期的な研修や、ヒヤリハット事例の共有、優良な現場の表彰など、社員が主体的に安全に取り組める仕掛けをつくることで、アルコールチェックは単なる形式ではなく会社の競争力を高める基盤になります。
【まとめ】法令遵守と現場安全を両立させるアルコールチェックのあり方

アルコールチェック制度は、単なる規制への対応にとどまるものではありません。建設業においては、ダンプカーやフォークリフト、重機といった一つひとつの車両が重大事故につながりかねないため、法令遵守と現場の安全確保をいかに両立させるかが重要な課題となります。
建設業における安全管理の次なる一歩
2022年から始まったアルコールチェックの義務化は、今やすべての建設会社にとって避けては通れないものとなりました。しかし、制度に従うだけでは十分とは言えません。
直行直帰の社員への対応や、遠隔地現場での検査体制、夜間工事のリスクなど、建設業特有の課題は山積しています。
これから求められるのは、最新の検知器やクラウドシステムを活用しつつ、現場実情に合わせた柔軟な運用を築くことです。
「事故ゼロ」に向けた企業姿勢の重要性
最終的に問われるのは、会社としての姿勢です。
「うちは義務だからやっている」ではなく、「社員と現場の安全を守るためにやっている」という姿勢を示すことが、事故防止はもちろん、取引先や発注者からの信頼にも直結します。
アルコールチェックはあくまで入口にすぎません。その先にあるのは、事故ゼロを実現するための企業文化づくりです。制度をうまく活かしながら、現場の安全と企業の持続的な成長を両立させていくことが、2025年以降の建設業に求められる次なる一歩だと言えるでしょう。