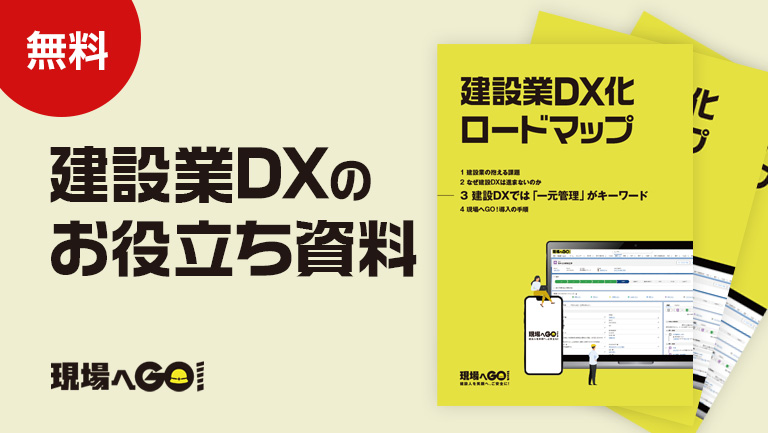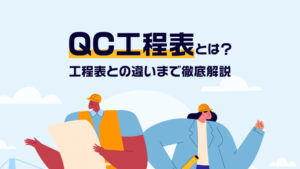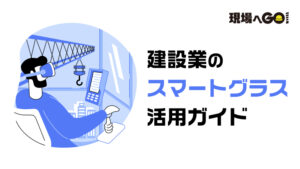建設業における労働安全衛生法(安衛法)とは?
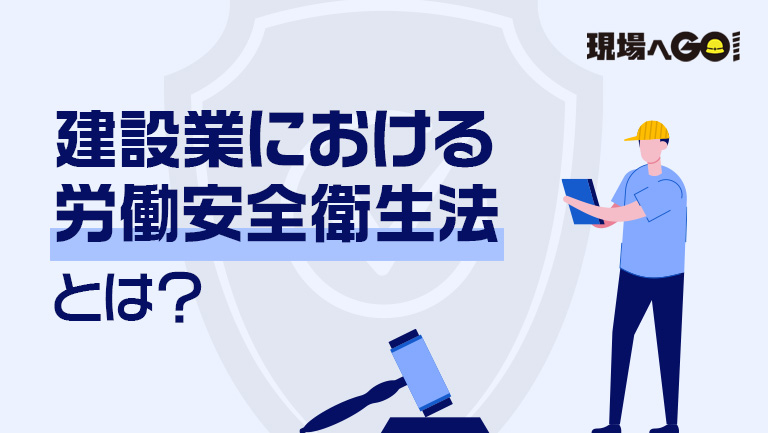
なぜ今「労働安全衛生法」が注目されているのか

建設現場において、労働災害をゼロにすることは長年の目標です。しかし現実には、墜落や転落、重機の接触といった事故が後を絶ちません。こうした背景から、近年あらためて「労働安全衛生法」に注目が集まっています。
特にここ数年は、働き方改革やデジタル化の流れもあり、安全管理の在り方にも変化が求められるようになってきました。紙や口頭での指示では対応しきれないことも多く、情報共有の精度やスピードが問われる時代になってきました。
さらに、厚生労働省は「安全衛生対策の強化」を掲げ、罰則の厳格化や事業者の責任明確化も進めています。これは単なる法律の問題ではなく、現場で働く一人ひとりの命と健康を守るために避けては通れないテーマです。
こうした流れの中で、「労働安全衛生法」をただ守るだけでなく、どう現場で「活かす」かが問われるようになっています。
労働安全衛生法とは?基本的な考え方と目的
労働安全衛生法(略して「安衛法」)は、働く人の「安全」と「健康」を守るために定められた法律です。昭和47年に施行されて以来、時代の変化に合わせて何度も改正されてきました。
この法律の一番の目的は、職場での事故や病気を未然に防ぎ、働く人が安心して仕事に向き合える環境をつくること。特に建設業のように危険を伴う作業が多い業種では、この法律の存在がより重要になります。
安衛法では、事業者には「危険の防止」「作業環境の整備」「健康管理」などについて具体的な責任が課されています。たとえば、高所作業の際の安全帯の使用、騒音や粉じんへの対策、定期的な健康診断の実施など、すべてこの法律に基づいた取り組みです。
ポイントは、単にルールを守るだけではなく、「現場の安全文化を育てる」という考え方が根底にあること。法律を理解し、活用することで、働く人も、現場を管理する人も、より良い仕事環境を作っていけるのです。
建設業で特に重要とされるポイント

建設現場は日々変化し、さまざまな危険がともなう場所でもあります。だからこそ、労働安全衛生法の中でも建設業に特化したルールや取り組みが重視されています。ここでは、現場で特に大切とされる3つのポイントを紹介します。
作業主任者の選任
高所作業や酸素欠乏の恐れがある場所、コンクリートの破砕作業など、特定の作業を行う際には「作業主任者」の選任が法律で義務づけられています。
作業主任者は、作業手順の確認や作業員への指示、安全装置の確認など、安全確保の中心的な役割を担う存在です。資格が必要なケースも多く、現場ではベテラン職人が選ばれることが一般的です。
高所作業・重機作業における安全対策
足場の設置・解体、屋根の上での作業、クレーンやバックホーなどの重機を使った作業は、事故につながるリスクが高いため、特に厳しい管理が求められます。
安全帯(フルハーネス)の着用はもちろん、作業前の点検やKY(危険予知)活動、誘導員の配置など、細かな安全対策の積み重ねが重要です。
危険物の取り扱いと保管管理
現場では、ガソリンやシンナー、ガスボンベなどの危険物を使用する場面もあります。これらは取り扱いを誤ると火災や爆発のリスクがあるため、専用の保管庫や消火器の設置、法定数量の確認など、しっかりとした管理体制が必要です。
また、作業員一人ひとりが取り扱い方法を理解していることも、安全のためには欠かせません。
安全管理の実務上の課題
いくら制度やルールが整っていても、現場での運用がうまくいかなければ意味がありません。建設業の現場では、実際に安全管理を行う中で、いくつか共通した課題が浮かび上がってきます。
情報共有の煩雑さ
安全に関する情報は多岐にわたります。作業手順、注意喚起、気象情報、使用機材の状態など、日々共有すべき内容は山ほどあります。しかし、そのほとんどが紙の書類や口頭で伝えられているため、情報の伝達ミスや見落としが発生しやすいのが実情です。また、関係者が多い現場ほど、全員に正しく情報を届けるのが難しくなります。
現場間でのルールのバラつき
同じ会社の現場でも、担当者の方針や協力会社の体制によって、安全に対する考え方やルールの運用が異なることがあります。「あっちの現場ではOKだったのに、こっちではダメと言われた」といった声が職人の間から上がるのも珍しくありません。こうしたルールのばらつきは、混乱や不満の原因となり、安全意識の低下にもつながります。
報告・記録の属人化
ヒヤリ・ハットの報告や点検記録、安全ミーティングの議事録など、本来は誰が見ても分かるように記録しておくべき情報が、個人の裁量に任されてしまっているケースも少なくありません。結果として「誰が何をやったのか」が曖昧になり、万が一の事故の際に責任の所在が不明確になってしまうこともあります。
ITツールを活用した労働安全衛生活動の効率化

現場の安全を守るうえで、日々の記録や情報共有、ルールの徹底は欠かせません。しかし、それらをすべて人力で対応しようとすると、どうしても「手間」や「抜け・漏れ」が出てきてしまうのが現実です。だからこそ、いま多くの建設現場で注目されているのが、ITツールの活用です。
手書きの報告書から、スマホでの入力へ
例えば、これまで紙に手書きしていた作業日報や点検チェックリストも、スマートフォンやタブレットから入力できるようになれば、現場で完結できます。作業が終わってから事務所に戻って記入する必要がなくなり、時間のロスを防ぐだけでなく、記録の正確性も高まります。
情報共有のスピードが段違い
ITツールを使えば、離れた現場同士でもリアルタイムで情報を共有できます。今日の注意点や、作業中に発見した不具合なども、その場で写真付きで報告が可能です。結果として、現場の「今」が見えるようになり、早めの対応や意思決定がしやすくなります。
ルールの徹底がしやすくなる
また、現場ごとにルールが異なると混乱が生まれやすくなりますが、ITツールを使ってマニュアルや注意事項を一元管理しておけば、「誰でも」「どこでも」「同じ内容」を確認できるようになります。新しく現場に入った人にも統一した情報を提供できるので、ルールの浸透がスムーズになります。
これからの安全管理に必要な視点
建設現場の安全管理は、単なるルールの遵守ではなく、現場の一人ひとりが「自分たちの命を守る行動」として取り組むことが大切です。労働安全衛生法が求めているのは、そうした意識を現場に根付かせるための「仕組みづくり」だと言えるでしょう。
とはいえ、現場ごとに忙しさや人手不足の事情もあり、安全対策が後回しになってしまうこともあります。そんな中で、誰でも簡単に使えるツールがあると、ルールの定着も進みやすくなります。
「現場へGO!」は、そうした現場のリアルな声に応える形で開発されており、安全管理を日々の業務の中に自然と組み込めるよう工夫されています。大げさな仕組みではなく、日々の点検や報告が自然と記録に残り、チーム全体で安全意識を高めていける。そんな流れをつくっていくことが、これからの現場には求められています。
安全管理に正解はありませんが、「続けられる仕組み」を持つことは、確かな第一歩です。法令を守るためだけでなく、現場で働く人たちが毎日を無事に終えられるために、今できることから少しずつ整えていきましょう。
「現場へGO!」でできること

建設現場の安全管理は、いかに「正確に」「早く」「みんなで」情報を共有できるかがカギになります。その点で、「現場へGO!」は現場のリアルな悩みに寄り添ったツールです。ここでは、実際にどんな使い方ができるのかを見ていきましょう。
リアルタイム情報共有で現場の「今」を全員で把握
「現場へGO!」を活用することで、現場での注意事項や不具合報告などの情報を、スマートフォンやタブレットから即座に共有できます。管理者や他のチームメンバーは、アプリを通じてリアルタイムで情報を受け取ることができ、必要なアクションを迅速に起こすことが可能です。また、共有された情報はクラウドに保存されるため、現場外からでも状況の確認が可能となり、チーム全体の連携がスムーズに進みます。
スケジュールとタスクの一元管理
「現場へGO!」では、Salesforceの標準機能を活用し、予定(行動)やToDo(タスク)を簡単に作成・管理できます。これにより、個人やチームのスケジュールを一元的に把握し、業務の抜け漏れを防止します。また、カレンダーを共有することで、同僚や上司の予定を確認しやすくなり、会議の調整や共同作業の計画がスムーズに行えます。
モバイルからのスケジュール確認と更新
スマートフォンやタブレットを使用して、外出先でもスケジュールを確認・更新できます。これにより、現場での迅速な対応が可能となり、作業の効率化が図れます。また、GoogleカレンダーやOffice365など、多くのカレンダーアプリとの連携も可能で、既存のツールとの統合が容易です。
行動(ToDo)の件名リストのカスタマイズ
管理者は、よく使用する行動やToDoの件名をリスト化し、ユーザーが選択しやすいようにカスタマイズできます。これにより、入力の手間を省き、統一された記録が可能になります。例えば、「現地調査」や「安全点検」など、現場特有のタスクを予めリストに追加することで、迅速な入力と情報の標準化が実現します。
案件との連携による進捗管理
行動やToDoを案件に関連付けることで、各案件の進捗状況を明確に把握できます。これにより、プロジェクト管理が効率的に行え、関係者全員が最新の情報を共有することが可能となります。また、工程表や関連資料をクラウド上で一元管理することで、過去の記録を簡単に検索・参照でき、報告書の作成や監査対応の手間も大きく減ります。