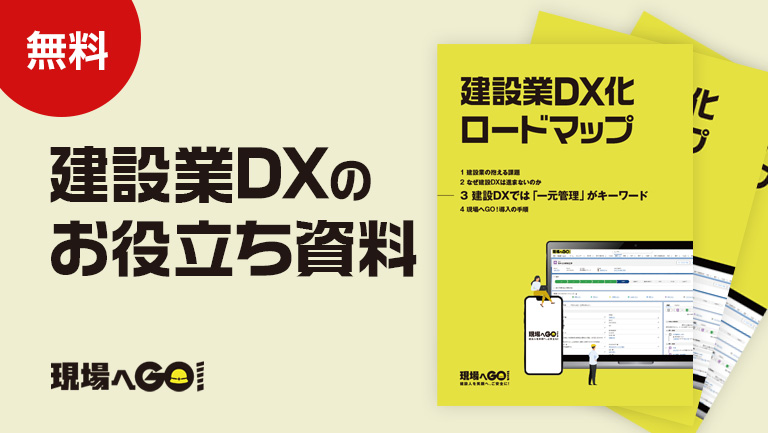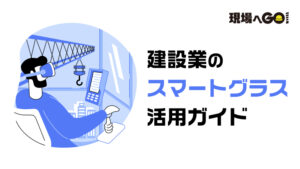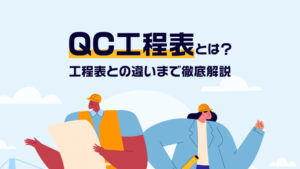建設業の遠隔臨場とは?国交省推進の仕組み・メリット・活用事例を徹底解説

はじめに ― 建設業で注目される「遠隔臨場」とは

近年の建設業界では、人手不足やコスト削減への対応が急務となっています。その中で注目を集めているのが「遠隔臨場」という取り組みです。従来であれば監督者や検査員が現場に足を運んで確認していた作業を、通信技術を活用して遠隔からチェックできるようにする仕組みで、現場の効率化と品質向上の両立を実現する方法として広がりつつあります。
特に国土交通省が主導して普及を進めていることもあり、公共工事をはじめ民間工事にも導入が拡大しています。今後の現場運営を考える上で、避けて通れないテーマのひとつになりつつあるといえるでしょう。
遠隔臨場の定義と基本的な仕組み
「遠隔臨場」とは、建設現場に設置したスマートグラスやモバイル端末、ウェアラブルカメラなどを使って、遠隔地にいる監督員や発注者がリアルタイムに現場状況を確認できる仕組みを指します。
従来の「写真での報告」や「事後の動画確認」と異なり、映像と音声を双方向でやり取りできる点が大きな特徴です。これにより、現場での検査や確認作業をわざわざ出張して行わなくても、事務所や別の現場からチェックできるようになります。
基本的な流れはシンプルで、現場スタッフが端末を操作し、カメラを通じて作業の進行状況を映し出し、監督者が遠隔で確認・指示を行います。必要に応じて映像や音声を記録することで、証跡管理にも役立ちます。
国土交通省が推進する背景
遠隔臨場が急速に注目されるようになった背景には、国土交通省の方針があります。国交省は2020年以降、建設業界の生産性向上と働き方改革を目的に、遠隔臨場の活用を積極的に推奨しています。
現場の移動時間を削減できることで、監督員の負担を軽減できるだけでなく、公共工事の品質確保やコスト削減にもつながるため、国の施策として導入が進められているのです。また、コロナ禍での対面業務の制約も後押しとなり、リモート技術の活用が一気に広がりました。
現在ではガイドラインも整備され、通信環境や端末要件、記録方法などが明確に示されています。これにより、地方の工務店や中小建設会社でも安心して導入できる環境が整いつつあります。
建設業における遠隔臨場のメリット
遠隔臨場は、単なる「移動時間を減らす便利な仕組み」にとどまりません。現場の負担を軽減しつつ、品質や安全性の向上にも直結するため、導入した企業からは「思った以上に効果が大きい」という声が少なくありません。ここでは、代表的なメリットを整理してみます。
現場移動の削減による業務効率化
これまで監督者や検査員は、現場ごとに移動して確認作業を行う必要がありました。特に地方や複数現場を抱える場合、移動だけで一日の大半を取られてしまうことも珍しくありません。
遠隔臨場を取り入れることで、事務所や別の現場にいながら確認作業が可能になります。その結果、移動時間や交通費が大幅に削減されるだけでなく、限られた人員をより多くの現場に振り分けることができます。結果として「少人数でも複数現場を効率的に回せる体制」を築けるのです。
写真・動画を超えたリアルタイム確認
これまでの現場報告は「写真を撮って送る」「作業後に動画を確認する」といった方法が主流でした。しかし、こうしたやり方では「撮影角度が足りない」「肝心な部分が映っていない」といった問題が起きやすいものです。
遠隔臨場では、監督者がリアルタイムで映像を見ながら「もう少し右にカメラを向けてください」「その部材を拡大してください」と具体的な指示を出せます。これにより、写真や録画では補えない細部まで確認でき、現場の状況を正確に把握できます。誤解や報告漏れを減らし、手戻りの防止にもつながります。
安全管理・品質管理の強化
建設現場では、安全と品質の確保が最優先課題です。遠隔臨場は、こうした管理面の強化にも大きな効果を発揮します。
例えば、安全帯の装着や保護具の使用状況をその場でチェックできるため、事故防止に直結します。また、コンクリート打設や鉄筋の配筋といった重要工程をリアルタイムで確認し、必要に応じてすぐに修正指示を出すことも可能です。
さらに、やり取りを記録しておけば、万が一トラブルが発生した際にも「いつ、どのように確認したか」という証跡が残ります。これは発注者にとっても施工者にとっても安心材料となり、信頼関係の構築にもつながります。
遠隔臨場の活用事例

コンクリート打設時の確認
コンクリート工事では、打設前にスランプ試験や温度管理を立ち会いで確認するのが従来の流れでした。遠隔臨場を使えば、現場スタッフがスマートグラスやカメラを通じて試験の様子を映し出し、発注者や監督は事務所にいながらリアルタイムで確認できます。現地移動の手間を省きつつ、従来どおりの品質確保が可能です。
鉄筋や型枠の出来形確認
鉄筋の配筋状況や型枠の組立て精度は、写真だけでは判断が難しい場合があります。そこで、遠隔臨場を活用し、カメラの角度を変えながら現場を映すことで、その場で質疑応答が可能になります。結果として、確認漏れややり直し工事のリスクを抑えられる点が大きなメリットです。
安全パトロールの効率化
従来の安全パトロールは、月に一度担当者が現場へ赴き、足場や保護具の状況をチェックしていました。遠隔臨場では、複数の現場をまとめてオンラインで確認でき、異常があれば即座に改善指示を出せます。安全管理を「点」から「面」へと広げられるのが強みです。
発注者検査や立会いの代替
公共工事などでは、発注者の検査や立会いが欠かせません。ただし遠方であれば時間もコストも大きな負担です。遠隔臨場を導入すれば、現場スタッフがカメラを操作しながら必要箇所を映し出し、発注者は事務所から確認して承認できます。移動を減らしながら検査の透明性を保てる点が評価されています。
専門技術者によるリモート支援
地盤改良や特殊な施工では、専門技術者の立会いが求められるケースもあります。遠隔臨場を活用すれば、専門家が全国どこからでも施工状況を見ながら助言でき、人材不足の課題にも対応できます。現場に常駐させる必要がなくなるため、効率的なリソース活用にもつながります。
遠隔臨場の課題と導入時の注意点
遠隔臨場は大きなメリットがある一方で、導入すればすぐに効果が出るわけではありません。実際に使い始めると「思った以上に通信が不安定」「機材の操作が現場でうまくいかない」といった声も聞かれます。ここでは、建設現場で導入を検討する際に押さえておきたい課題と注意点を整理してみましょう。
通信環境(Wi-Fi・5G)の整備
遠隔臨場の前提となるのは、安定した通信環境です。どれほど高性能なカメラやシステムを導入しても、映像が途切れたり音声が遅延したりすれば、確認作業がスムーズに進みません。
都市部の現場では比較的通信環境が整っていますが、山間部や地下工事のような場所では電波が不安定になることがあります。そのため、事前に現場の電波状況を調査し、必要に応じてモバイルルーターや外部アンテナを用意することが重要です。最近は5Gの活用も進んでいますが、実際には4G回線を併用するケースも少なくありません。
機材・システムの選定ポイント
遠隔臨場をスムーズに活用するためには、機材やシステムの選定も欠かせません。カメラの画質や防水性、バッテリーの持続時間などは現場作業に直結するため、価格だけで決めてしまうと後で不便を感じることになります。
また、システムについても「発注者側と施工者側で同じプラットフォームを利用できるか」「記録データをどう保存するか」といった点を確認しておく必要があります。導入コストは抑えつつも、現場での使いやすさを優先した選択が望ましいでしょう。
現場スタッフへの教育と運用ルールづくり
機材やシステムを整えても、実際に操作するのは現場スタッフです。スマートフォンやタブレットの扱いに慣れている人もいれば、デジタル機器が苦手な人もいます。そのため、誰でも同じ手順で操作できるように、マニュアルを整備したり事前に研修を行ったりすることが欠かせません。
さらに、通信する時間帯や記録データの管理方法など、運用ルールを明確にしておくことも大切です。こうした準備をしておかないと、せっかく導入しても「人によって使い方がバラバラ」「データが散らかって確認に手間がかかる」といった事態になりかねません。
遠隔臨場は便利な仕組みですが、環境整備やルールづくりを怠ると効果が半減してしまいます。導入を成功させるには、「通信環境」「機材」「人材」の3つをバランスよく整えることがポイントです。
遠隔臨場を支えるICT施工・DXの流れ

遠隔臨場は単なる便利な仕組みではなく、建設業におけるICT施工やDX推進の流れの中で位置づけられています。現場の効率化や人材不足への対応という個別の課題解決だけでなく、業界全体の生産性向上や働き方改革につながる取り組みのひとつといえるでしょう。
建設業におけるDX推進との関係
近年、建設業界でも「DX(デジタルトランスフォーメーション)」がキーワードになっています。紙での帳票や現場写真をデジタル化する取り組みはもちろん、AIやIoTを活用した施工管理、クラウドを使った情報共有などが広がっています。
遠隔臨場もその一環として注目されており、現場と事務所、発注者をデジタルで結ぶ仕組みとして位置づけられます。単純に移動を減らすだけでなく、「現場情報をリアルタイムで共有し、全員が同じ情報を基に判断できる」環境を作ることが、DXの核心につながっています。
BIM/CIMとの連携可能性
遠隔臨場の将来的な発展を考えるうえで重要なのが、BIM/CIMとの連携です。BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)は、建物や土木構造物を3Dモデルで可視化し、設計から施工、維持管理までを効率化する仕組みです。
例えば、現場から送られる映像をBIMモデルと照らし合わせることで、「設計通りに施工されているか」を瞬時に確認することが可能になります。これまで別々に行われていた「現場確認」と「設計図面のチェック」がシームレスにつながれば、より精度の高い施工管理が実現します。
他社事例から学ぶ活用シーン
すでに遠隔臨場を取り入れている企業では、さまざまな活用シーンが報告されています。あるゼネコンでは、鉄筋の配筋検査を遠隔で実施することで、従来のように監督者が現場に常駐する必要がなくなり、検査時間を大幅に短縮できたといいます。
また、中小規模の工務店でも、発注者との立ち会い確認を遠隔で行い、双方の移動負担を軽減した事例があります。これにより、施主や発注者がわざわざ現場に出向かなくても工事の進捗を確認できるようになり、顧客満足度の向上にもつながっています。
こうした実例は「自社でも取り入れられるのではないか」という気づきを与えてくれるものです。単なるコスト削減ではなく、現場の信頼性を高めるツールとして活用できる点に、遠隔臨場の真価があります。
遠隔臨場を導入するステップ
遠隔臨場はメリットが大きい一方で、いきなり全社的に導入してしまうと混乱を招く恐れがあります。効果を確実に得るためには、段階を踏んで少しずつ進めていくことが大切です。ここでは、導入の流れを3つのステップに整理してみましょう。
現行業務フローの棚卸し
最初のステップは、自社の業務フローをしっかり把握することです。
「どの工程で立ち会い確認が多いか」「検査や承認にどれくらいの時間がかかっているか」などを洗い出すことで、遠隔臨場が効果を発揮しやすい場面が見えてきます。
この棚卸しをせずに導入してしまうと、「結局は従来と同じ手間がかかる」「使わなくても済む場面にまで無理やり適用してしまう」といった状況になりかねません。まずは自社の課題を整理し、改善ポイントを明確にしておくことが成功の第一歩です。
小規模現場でのテスト導入
次のステップは、小規模な現場や特定の工程に限定して試験的に導入することです。
いきなり全現場に展開するのではなく、「鉄筋検査だけ遠隔臨場でやってみる」「一つの工事現場で一定期間テストする」といった形で始めると、現場の負担を抑えつつノウハウを蓄積できます。
テスト導入の段階では、通信状況の確認や、スタッフの操作習熟度を把握することも大切です。ここで得られた課題を改善してから次の段階に進むことで、失敗リスクを最小限に抑えることができます。
本格展開に向けた体制づくり
最後のステップは、本格導入に向けた社内体制の整備です。
運用ルールをマニュアル化し、研修やサポート体制を整えることで、誰でも同じ水準で遠隔臨場を活用できるようになります。加えて、発注者や協力会社との情報共有方法を決めておくことも重要です。
また、導入後の効果を定期的に評価し、「移動コストはどれだけ削減できたか」「確認精度はどう向上したか」といった数値を見える化することで、経営層や現場双方の納得感を高められます。
段階を踏んで導入を進めれば、遠隔臨場は単なる便利ツールではなく、組織全体の生産性を底上げする仕組みになります。焦らず、一歩ずつ取り入れることが成功のカギです。
まとめ ― 遠隔臨場で変わる建設現場の未来

遠隔臨場は、単なる作業効率化の手段にとどまらず、建設現場のあり方そのものを変えていく可能性を秘めています。少子高齢化や人材不足が深刻化する中、限られたリソースでより高品質な施工を実現するための有力な選択肢となりつつあります。
DX推進と「遠隔臨場」の位置づけ
国土交通省が推進する建設DXの流れの中で、遠隔臨場は欠かせない要素のひとつです。
単発的な便利ツールではなく、クラウドやBIM/CIMといった他のデジタル技術と組み合わせることで、現場と事務所、発注者の三者が同じ情報を共有しながら意思決定できる体制を築けます。
これからの建設業に求められる働き方改革と安全管理
遠隔臨場の普及は、単に「現場に行かなくて済む」ことだけを意味しません。長時間労働の是正や働き方改革、安全管理の高度化といった、業界全体の課題に直結しています。
若手人材や女性、海外技能実習生など、多様な人材が活躍しやすい環境を整えるうえでも、遠隔臨場は有効な仕組みといえるでしょう。
自社にあった導入ステップの考え方
全ての企業に同じ方法が当てはまるわけではありません。通信環境、現場の規模、発注者との関係性などによって、導入の形は異なります。
重要なのは「自社にとってどの部分で最も効果が出るか」を見極め、小さく始めて徐々に広げていくことです。無理に一度で全てを変えようとする必要はありません。
遠隔臨場は、未来の建設業を支える基盤技術のひとつになるといっても過言ではありません。効率化だけでなく、信頼性と安全性を高める取り組みとして、これからますます普及していくでしょう。
現場へGO!のご紹介
遠隔臨場を導入するにあたって、「どのように日常業務と組み合わせるか」が大きな課題になります。そこで役立つのが、建設業向け業務効率化アプリ 「現場へGO!」 です。
遠隔臨場にも対応できる業務効率化アプリ
「現場へGO!」は、現場での写真撮影・作業記録・進捗報告をアプリひとつで完結できるツールです。
遠隔臨場で必要となる現場映像や記録の共有もスムーズに行えるため、発注者や監督者とのやり取りを効率化できます。従来のように紙の帳票を整理したり、複数のアプリを使い分けたりする必要がなくなるのが大きな強みです。
現場記録・進捗管理・安全管理を一元化
遠隔臨場を進めるうえで重要なのは、「現場情報の一元管理」です。
「現場へGO!」を活用すれば、写真や動画、検査記録、安全管理データをクラウド上にまとめて保存できます。
必要なときにすぐに情報を取り出せるため、監督者や発注者とのコミュニケーションが格段にスムーズになり、確認作業の信頼性も高まります。
建設業界におけるDXの流れは、これからさらに加速していきます。
遠隔臨場を効果的に取り入れるためにも、まずは「現場へGO!」で日常業務のデジタル化を進めてみてはいかがでしょうか。