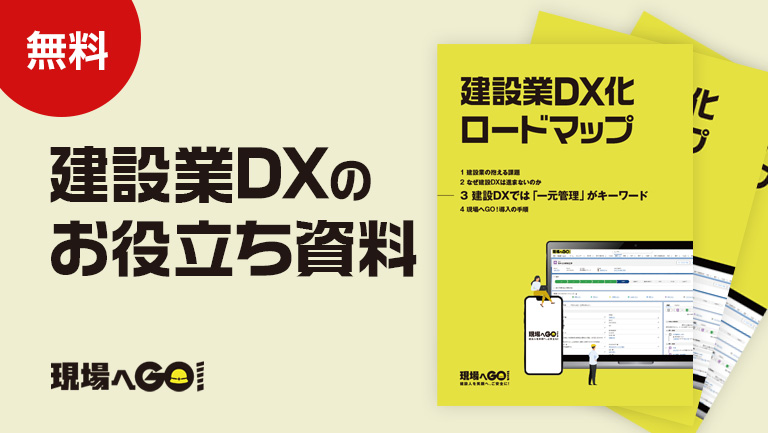建設業のスマートグラス活用ガイド|基本機能からDX事例・導入ポイントまで
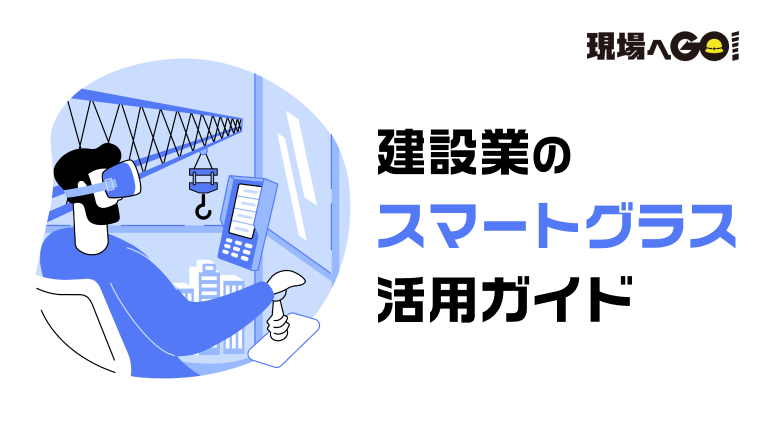
スマートグラスとは?建設業界で注目される理由

スマートグラスの基本機能
スマートグラスは、一見すると普通のメガネ型のデバイスですが、内部には小型のディスプレイやカメラ、マイクなどが搭載されています。代表的な機能は次のとおりです。
- カメラ機能:作業者の目線で映像や写真を撮影でき、現場の状況をそのまま共有可能。
- AR表示:図面や手順書などの情報をレンズ越しに重ねて表示。両手を使った作業中でも必要な情報を確認できる。
- 音声操作:手がふさがっている状態でも、音声コマンドで操作ができる。
- 通信機能:Wi-Fiや5Gを使って、遠隔地の担当者と映像・音声をリアルタイムでやりとりできる。
これらの機能によって、従来は紙の資料やタブレットで確認していた情報を「視界に映し出す」ことが可能になり、現場の負担を大きく軽減できます。
なぜ今、建設業で導入が進んでいるのか
建設業界でスマートグラスが注目を集めている背景には、いくつかの社会的・業界的な要因があります。
- 深刻な人手不足
若手人材の不足やベテランの引退により、現場の技術をどう継承するかが課題になっています。スマートグラスを使えば、熟練者が遠隔から新人をサポートでき、教育コストや時間を大幅に削減できます。 - 安全対策の強化
建設現場では「視線をそらす」ことが事故につながるケースもあります。スマートグラスなら、資料を手に持たずに確認できるため、作業中でも周囲への注意を怠りにくく、安全性が高まります。 - 作業効率の向上
紙図面を探したり、事務所へ戻って確認する手間は意外に大きなロスです。必要な情報を目の前に表示できるスマートグラスは、移動や確認作業の時間を削減し、結果として全体の工期短縮にもつながります。
つまり、スマートグラスは「現場の人手不足」「安全性の確保」「効率化」という、いま建設業界が直面している3つの大きな課題に対して有効な解決策となり得るのです。
建設業におけるスマートグラスの活用シーン
遠隔での現場支援(本社やベテランからの指示)
これまで、現場で分からないことがあれば、電話やメールでやり取りするしかありませんでした。しかし、文章や口頭だけでは状況を正確に伝えるのは難しく、結局ベテラン社員が現場まで足を運ぶ…というのがよくあるパターンです。
スマートグラスを使えば、作業者の視点そのままの映像を本社やベテランに中継できます。遠隔からでも「そこは右じゃなくて左にボルトを回して」「その部材の向きが違う」と即座に指示でき、移動コストをかけずにトラブルを解決できるのです。
安全管理・作業記録(ハンズフリーでの写真・動画撮影)
安全パトロールや施工記録を残すとき、これまでは片手にカメラを持って撮影していた方も多いはずです。しかし、手がふさがること自体がリスクにもなりかねません。
スマートグラスなら、作業を止めずに音声操作で写真や動画を撮影できます。作業員が普段通りに作業しながら記録が残せるので、事故のリスクを減らしつつ、記録の抜け漏れも防げます。また、日時や位置情報とあわせて保存できるタイプもあり、後からのチェックや報告書作成にも役立ちます。
設計図・施工手順のAR表示
「図面を見たいけれど、いちいち紙を広げたりタブレットを操作したりするのが面倒」そんな場面は少なくありません。スマートグラスなら、視界に直接図面や施工手順を表示できるため、両手を使った作業を中断せずに確認できます。
例えば配管工事の現場で、配管の取り回しをARで重ねて表示すれば「どこに設置すべきか」が一目で分かります。これにより施工ミスが減り、やり直しによる余計な工数も削減できます。
教育・研修(新人育成、技能伝承の効率化)
建設業における大きな課題のひとつが、技能の継承です。ベテランの「勘やコツ」は、口頭ではなかなか伝わりにくいものです。
スマートグラスを活用すれば、ベテランの作業をそのまま動画で記録したり、新人の視点をリアルタイムで共有しながら指導したりすることが可能です。従来の座学や集合研修よりも実践的で効率が良く、教育スピードを上げながら品質も確保できます。
このように、スマートグラスは「遠隔支援」「安全記録」「施工支援」「教育」という、建設業の主要な現場ニーズをカバーできるツールです。単なる便利アイテムではなく、現場の課題解決に直結する実用的なDX機器として位置づけられるようになってきています。
スマートグラス導入のメリット

作業効率アップ(移動・紙資料の削減)
建設現場では「必要な資料が事務所に置いてある」「担当者に確認しないと分からない」といった理由で、無駄な移動が発生することが少なくありません。特に大規模な現場では、一度の往復だけでも大きな時間ロスになります。
スマートグラスを導入すれば、設計図や施工手順をその場で表示できるため、移動時間をほぼゼロにできます。また、紙の図面をめくる手間や、汚れや破損の心配もなくなり、効率的に作業を進められます。
コスト削減(出張や再工事の防止)
「現場で問題が発生 → ベテラン社員が出張 → 解決」という流れは、交通費や人件費が大きな負担になります。スマートグラスを使えば、現場の映像をリアルタイムで共有できるため、出張自体が不要になるケースも増えます。
さらに、施工中のミスを早期に発見できるため、完成後のやり直しや再工事を防ぐことができます。出張費と手戻りコスト、この二つが抑えられるだけでも、導入費用の元は十分に取れると言えるでしょう。
安全性の向上(危険箇所の見える化)
建設現場では「ちょっと確認したい」と視線を逸らすだけで、事故につながる危険があります。スマートグラスなら、視界の中に必要な情報を映し出せるため、常に周囲を確認しながら作業を進められます。
また、遠隔で現場を見ている管理者が「その足場は不安定だ」「後ろに重機が来ている」と即座に指摘できるのも大きなメリットです。作業員本人が気付きにくいリスクを“第三の目”でカバーできる点は、安全管理の強化に直結します。
品質向上と記録の一元管理
施工の品質を維持するには、作業内容を正確に記録し、後から確認できるようにしておくことが欠かせません。従来は写真をデジカメで撮影し、あとでPCに取り込み、報告書にまとめる…といった手間がかかっていました。
スマートグラスなら、作業者の目線で撮影した記録をクラウドに自動保存でき、報告や共有もスムーズに行えます。これにより「誰が、いつ、どんな作業をしたか」が一目で分かり、品質管理の精度が格段に上がります。
このように、スマートグラスは「効率」「コスト」「安全」「品質」という建設業の4大テーマに直結するメリットをもたらします。単なる便利ガジェットではなく、現場運営そのものを変革する可能性を持ったツールなのです。
導入時の課題と解決策
現場スタッフの操作習熟
新しいデバイスを導入するときに必ず出てくるのが「操作が難しそう」「自分に使いこなせるだろうか」という不安です。特に建設現場では年齢層も幅広く、デジタルに不慣れな方も少なくありません。
解決策としては、段階的な研修やマニュアル動画の整備が効果的です。スマートグラスは音声操作や直感的なUIを備えているものが多いため、基本操作に慣れてしまえば数日で実務に活用できるケースも多いです。
通信環境(Wi-Fi・5G)の確保
「現場で映像が途切れてしまう」「山間部で電波が弱い」といった通信トラブルは、スマートグラス活用の大きな壁になります。
解決策としては、モバイルルーターの活用やローカル保存機能付きの機種を選ぶことです。最近では5Gエリアも広がりつつあり、通信環境は着実に改善しています。将来的には建設現場用の専用ネットワークが普及する可能性もあり、この課題は時間とともに解消に向かうと考えられます。
機器の耐久性・バッテリー問題
建設現場は粉塵や振動、気温変化など、機械にとっては厳しい環境です。「壊れやすいのでは?」「バッテリーがすぐ切れるのでは?」という心配もよく聞かれます。
解決策は、防塵・防水規格に対応した現場向けモデルを選ぶこと。また、予備バッテリーやモバイルバッテリーを携行する運用ルールを整えておけば、一日の作業にも十分対応できます。最近の製品は産業向けを意識して作られているため、以前よりも耐久性は格段に向上しています。
プライバシー・セキュリティの懸念と対応策
スマートグラスは「現場の映像をそのまま外部に送信する」性質があるため、情報漏えいやプライバシーへの配慮が欠かせません。例えば、施主や近隣住民が映り込むケースも想定されます。
解決策は、利用ルールと権限管理の明確化です。撮影データはクラウド上で暗号化して保管し、アクセスできる人を限定することが重要です。また、撮影前に関係者へ周知しておくなど、現場マナーとしての運用ルールも整備しておくと安心です。
このように、スマートグラス導入にはいくつかの課題が伴いますが、いずれも「製品の選び方」と「運用体制の工夫」で解決可能です。導入前に課題を洗い出しておけば、現場での定着もスムーズに進むでしょう。
建設業に適したスマートグラスの選び方

現場環境に合う機能(防塵・防水・耐衝撃)
建設現場は、ほこり・泥・雨・振動といった過酷な環境が日常です。一般的な電子機器ではすぐに壊れてしまう恐れがあります。そのため、防塵・防水性能を示す「IP規格」や、落下・衝撃に耐えられるかどうかは必ず確認したいポイントです。特に屋外作業が多い会社では、ヘルメットに装着できるタイプや、夏場でも熱に強いモデルを選ぶと安心です。
AR対応か、カメラ機能中心か
スマートグラスといっても、機種によって得意分野は異なります。
- AR表示重視のモデル:図面や手順書を目の前に映し出す機能が強く、施工支援や教育に向いています。
- カメラ機能重視のモデル:現場の映像をそのまま中継する用途に強く、遠隔支援や安全管理に適しています。
自社が「何を一番解決したいのか」を整理した上で、機能を選ぶことが大切です。最初から多機能を求めすぎるとコストが膨らむため、用途に絞った選択をすると失敗しにくくなります。
連携できるアプリやソフトウェア
スマートグラス単体では便利さが半減してしまいます。施工管理アプリ、図面共有システム、クラウドストレージなど、既存のDXツールとスムーズに連携できるかは必ずチェックしたいところです。
例えば、写真を撮影したら自動でクラウドにアップロードされ、現場日報や報告書に反映できるような仕組みがあれば、事務作業の負担がぐっと減ります。導入前に「自社のシステムとつなげられるかどうか」を確認しておくと、運用後の手戻りを防げます。
サポート体制とコスト(導入費用・運用費用)
機器の性能が良くても、サポートが不十分では現場に定着しません。特に初期設定や不具合時の対応、使い方に関するヘルプ体制が整っているかは重要です。
また、コスト面では「端末代」だけでなく、アプリ利用料やクラウドサービスの月額費用も含めて試算する必要があります。導入初期に費用がかかっても、出張削減や作業効率化でどのくらい回収できるか、投資対効果を見積もる視点が欠かせません。
建設業向けのスマートグラス選びは、単なるスペック比較ではなく「現場で使えるか」「既存システムとつながるか」「コストに見合うか」という3点で判断するのがポイントです。自社の課題に最もフィットする一台を選ぶことが、導入成功への近道となります。
スマートグラス×DXアプリで広がる可能性
現場管理アプリとの連携(報告・記録・共有)
スマートグラス単体でも便利ですが、真価を発揮するのは 現場管理アプリと組み合わせたとき です。
例えば、作業員が音声で「配管工事 完了」と指示すると、自動で写真が撮影され、そのまま日報や施工記録に反映される仕組みを作ることができます。これまで事務所に戻ってからPCで入力していた作業報告が、その場で完結するわけです。
写真・動画・コメントがクラウドで一元管理されれば、監督者や協力会社との情報共有もスムーズになり、報告業務にかかる時間を大幅に短縮できます。
BIMや施工管理システムとの統合
近年、建設業ではBIM(Building Information Modeling)の普及が進んでいます。スマートグラスとBIMを連携させれば、設計データを現場にAR表示し、施工中の状態とリアルタイムで照合することが可能です。
例えば「この配管は設計図どおりに設置されているか?」をその場で確認できれば、後戻り工事を減らし、品質も安定します。施工管理システムとの統合によって、工程管理や進捗確認も現場視点で行えるようになり、従来の“紙やPC中心の管理”から大きく前進するでしょう。
将来的なAI活用(自動認識、危険予知など)
今後の発展が期待されるのが、AIとの組み合わせです。
スマートグラスのカメラが現場を映し出し、AIがそれを解析することで、
- 危険な姿勢や動線を検出して警告
- 使用している工具や部材を自動認識して作業を記録
- 過去データと照合して施工不良の兆候を早期に発見
といった活用が可能になります。まさに「人間の目」と「AIの分析力」を組み合わせることで、現場の安全性と効率性が飛躍的に高まるのです。
スマートグラスは、単体の機器として見ると便利なアイテムにとどまります。しかし、DXアプリやBIM、AIといった仕組みと連携させることで、建設現場全体の生産性を底上げするプラットフォームへと進化していきます。今はまだ始まりの段階ですが、数年後には「スマートグラスがある現場が当たり前」になるかもしれません。
導入事例(建設業界での具体的な活用例)

遠隔支援による業務効率化
複数の現場を抱える建設会社では、現場ごとに熟練技術者を派遣するのは大きな負担です。スマートグラスを導入することで、現場作業員が映像をリアルタイムで共有し、本社や別拠点にいる技術者から直接指示を受けられる仕組みが整います。
これにより、移動時間や出張コストを減らせるだけでなく、施工中の判断もスピーディーに行えるようになります。特に海外や遠隔地の現場でも、同じ視点で状況を確認できるため、意思決定の迅速化に大きく貢献します。
中小規模現場での監督支援
人員が限られる小規模な現場では、監督者が複数の現場を掛け持ちするケースが少なくありません。スマートグラスを使えば、作業員が現場の映像を送ることで、監督者は移動せずに複数現場を把握し、必要な指示を行えます。
その結果、移動にかかる負担が減り、監督者がより効率的に現場を管理できるようになります。また、映像を記録として残せるため、施主への報告やアフターフォローにも活用され、顧客満足度向上につながるケースもあります。
技能教育・研修での活用
熟練作業員の高齢化や人材不足により、技能の継承は建設業界における大きな課題です。スマートグラスを使った教育研修では、現場作業をしながらベテランの作業手順映像を確認できるため、理解度が高まり、習熟までの時間を短縮できます。
また、危険な作業を遠隔で指導できる点も大きな特徴で、新人が安心して学べる環境をつくりやすくなります。録画機能を使えば、自分の作業を振り返って復習することもでき、教育の効率化にもつながります。
スマートグラスは「大手企業の効率化」だけでなく、「中小企業の管理負担軽減」や「人材育成」にも幅広く応用可能です。規模や業務内容に応じて導入方法を工夫することで、建設業における課題解決の有力な手段となるでしょう。有。ベテランがその場で指示を出せるようになり、移動コストは大幅に削減されました。特に海外プロジェクトでは「1回の出張で数百万円かかっていた出費が、ほぼゼロになった」という効果があり、経営層からも高く評価されています。
中小建設会社でのコスト削減事例
地方の中小建設会社では、現場監督が少数で複数の現場を兼任することが課題でした。そこでスマートグラスを導入し、現場の作業員が状況を映像で送ることで、監督者が現場を行き来しなくても指示を出せる体制を構築しました。
結果として、移動にかかっていた時間とガソリン代が削減され、監督者はより多くの現場を効率的に管理できるようになりました。また、映像を記録として残せるため、施主への説明やアフターフォローにも役立ち、顧客満足度の向上にもつながっています。
教育研修での成功事例
ある建設会社では、ベテラン作業員の高齢化に伴い、技能の伝承が急務となっていました。そこでスマートグラスを使った教育研修を開始。新人が現場で作業するときに、ベテランの作業手順を録画した映像をスマートグラス上に表示しながら学べる仕組みを導入しました。
従来の「口頭で説明 → 実際にやってみる」スタイルに比べ、理解度が高まり、習熟スピードが早まったと評価されています。また、危険な作業を遠隔で指導できるため、新人が安心してチャレンジできる環境づくりにもつながりました。
これらの事例から分かるのは、スマートグラスが「大手企業の効率化」だけでなく、「中小企業のコスト削減」や「教育現場の革新」にも幅広く応用できるという点です。規模や用途に関わらず、自社の課題に合わせて導入を進められるのが大きな魅力だと言えるでしょう。
まとめ:スマートグラスで変わる建設業の未来
DX推進と「スマートグラス」の位置づけ
建設業界のDXは、単なるデジタル化ではなく、現場の生産性・安全性を根本から変えていく取り組みです。その中でスマートグラスは、現場とオフィスをリアルタイムでつなぎ、紙や移動に依存していた従来のやり方を刷新する存在として注目されています。
これからの建設業に求められる働き方改革と安全管理
人手不足や高齢化が進む建設業界において、「効率的に働くこと」と「安全を確保すること」は避けられない課題です。スマートグラスを活用すれば、遠隔からの支援やAIによる危険予知などにより、無理のない働き方とリスクの少ない現場運営を両立できます。これは、これからの建設業に求められる“新しい働き方改革”の一環と言えるでしょう。
自社にあった導入ステップの考え方
一方で、すぐに大規模な投資をする必要はありません。
- まずは 特定の現場で試験導入
- その後、 教育や安全管理など他部門へ拡大
- 最終的に、 DX全体の仕組みに統合
というステップで進めれば、現場への負担も少なく、定着しやすくなります。重要なのは「自社の課題に合った使い方」を見極めることです。
建設DXアプリ「現場へGO!」のご紹介
スマートグラスを導入しても、データがバラバラでは効果は半減してしまいます。そこで役立つのが、建設業向けDXアプリ「現場へGO!」 です。
現場写真の管理や日報作成、施工記録の共有までを一元化できるため、スマートグラスで撮影した映像や写真もスムーズに活用可能。現場とオフィスをシームレスにつなげ、DX推進をさらに後押しします。