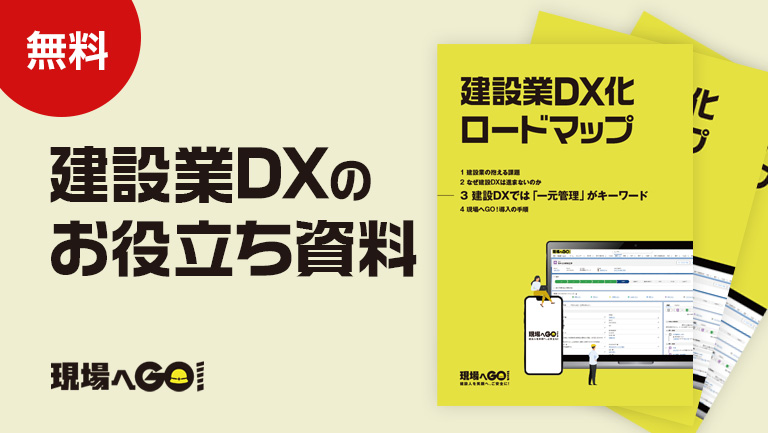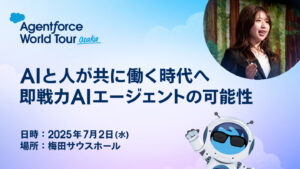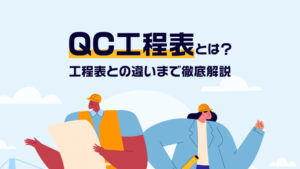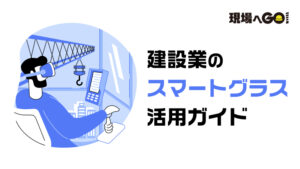【建設業向け】Salesforce導入のメリットと活用事例

建設業界を取り巻く課題と変化

人手不足・高齢化・属人化による現場運営の課題
建設業界では今、多くの企業が共通して抱えている構造的な問題があります。そのひとつが慢性的な人手不足です。特に若手人材の確保が困難で、技能労働者の平均年齢は年々上昇しています。現場の担い手が減りつつある一方で、ベテラン技術者の退職が進んでおり、技術の継承や作業の安定性にも支障が出始めているのが実情です。
さらに深刻なのが、業務の属人化です。たとえば「この案件は〇〇さんでないと分からない」「見積の根拠がその人の頭の中にある」といった状況は、会社の持続性を脅かすリスクになります。特定の担当者が不在になるだけで現場が止まってしまうような事例も、決して珍しくありません。
このような課題が重なることで、業務の非効率性が放置され、企業としての成長や事業拡大にブレーキがかかっている企業も少なくないのが現状です。
IT化の遅れとその影響
他業種に比べ、建設業界ではIT導入の遅れが目立ちます。業務プロセスが複雑かつ現場中心であることから、紙やExcel、電話・FAXといった従来型の運用が根強く残っています。
たとえば、案件ごとの進捗や見積、取引先情報などがバラバラに管理されていると、情報の確認に手間がかかり、ミスや重複対応の原因になります。情報が一元化されていないことが、社内コミュニケーションや意思決定のスピードに直接影響しているのです。
加えて、現場とオフィスとの情報のやり取りが非効率であるため、報告・連絡・指示系統にタイムラグが生じ、品質管理や顧客対応の面でも課題が残ります。
DX(デジタルトランスフォーメーション)への関心の高まり
こうした背景から、近年ではDX(デジタルトランスフォーメーション)への関心が建設業界でも急速に高まっています。単に業務をデジタル化するだけでなく、「情報の見える化」や「業務の標準化」「意思決定の迅速化」といった本質的な業務改革を目指す動きが活発になってきています。
特に中堅・中小の建設企業においては、「限られた人材で最大の成果を出すにはどうすればよいか」を考える中で、ITツールを活用して業務を効率化し、組織としての生産性を上げるという視点が不可欠になってきています。
これからの建設業では、経験と勘に頼る体質から、データと仕組みを活かす体制へと転換できるかどうかが、大きな分かれ目になると言えるでしょう。
Salesforceとは?建設業に求められるITツールの本質
Salesforceの概要と強み(クラウド型・拡張性・信頼性)
Salesforce(セールスフォース)は、世界中で多くの企業に導入されているクラウド型のCRM(顧客関係管理)プラットフォームです。営業支援、マーケティング、自動化、データ分析など、企業のフロント業務を中心に幅広くカバーできることが最大の特徴です。
建設業においても、顧客・取引先とのやりとり、案件の進捗、見積や契約の履歴など、一つ一つの情報が蓄積されていくプロセス管理ツールとして、大きな価値を持ちます。
またSalesforceはクラウド型であるため、社内ネットワークに依存せず、外出先や現場からも情報にアクセス可能です。さらに、豊富な外部連携・カスタマイズ性により、業種・業態ごとに柔軟にフィットさせられるのも、他のITツールと一線を画すポイントです。
信頼性やセキュリティ面でも評価が高く、公共事業や大手建設企業での採用実績も増加しています。
なぜ今、建設業にCRMが必要なのか
建設業では、顧客や元請け、下請け、設計会社など、多層的な取引先との関係が複雑に絡み合うのが特徴です。また、案件ごとに関わるメンバーが異なり、同じ顧客に対しても別の部署や担当者が対応することがあります。
こうした状況で、対応履歴や過去案件の記録がバラバラなままでは、営業活動や受注機会のロスが発生しやすくなります。CRMを導入することで、
- 顧客との接点を部門間で共有できる
- 過去の問い合わせ内容や見積履歴を即座に確認できる
- 担当者が変わっても継続的な対応が可能になる
といった効果が生まれ、取引先との関係性を長期的に強化する土台が築かれます。
営業マンの経験や感覚に頼っていた部分を可視化・仕組み化することで、組織としての営業力の底上げにもつながるのです。
Salesforceが選ばれる理由
建設業においてCRMを導入する上で、なぜSalesforceが注目されるのか。それは、以下のような理由によるものです。
- 建設業向けにカスタマイズしやすい柔軟性
営業・見積・契約・アフター対応など、各業務を横断的に設計できる。 - スモールスタートが可能
最初は限られた機能から導入し、徐々に拡張することができるため、ITに不慣れな現場でも取り入れやすい。 - API連携や拡張アプリが豊富
既存の見積ソフトや会計ソフトとの連携も視野に入れた設計が可能。 - 継続的なバージョンアップとサポート
クラウドならではの定期アップデートにより、常に最新機能を利用できる。
こうした総合力により、Salesforceは単なる「顧客台帳」ではなく、建設業務全体を支える基幹ツールとしての位置づけを確立しつつあります。
建設業でSalesforceを活用する主な領域と機能

顧客管理・取引先との情報共有
建設業において、顧客や元請け・下請け、協力会社との関係性は複雑かつ長期にわたる傾向があります。Salesforceの顧客管理機能(CRM)は、こうした多様な関係者との接点や履歴を一元的に記録・管理するのに最適です。
具体的には、営業活動や打ち合わせ内容、過去の見積履歴、クレーム対応の記録などを、案件ごと・企業ごとに紐づけて蓄積できます。これにより、
- 顧客対応の質が標準化される
- 担当者変更時も引き継ぎがスムーズになる
- 社内の誰がどの顧客とどんな関係を築いているかが可視化される
といったメリットが生まれ、営業活動の抜け漏れや重複対応を防ぐことができます。
案件管理・営業活動の可視化
建設業の案件は、問い合わせから見積、契約、施工までのプロセスが長期化することが一般的です。Salesforceでは、営業プロセスをフェーズごとに分解し、案件単位で一貫して管理することが可能です。
商談の状況や次のアクション、提案中の金額、競合状況などをリアルタイムで把握でき、進捗の停滞や抜けを防ぐ仕組みが構築できます。
加えて、ダッシュボードやレポート機能を活用すれば、営業部門全体の案件数や受注見込み額、フェーズ別の成約率などを可視化し、戦略的な営業マネジメントにもつなげることができます。
見積・契約・入札の管理プロセス
多くの建設会社では、見積や契約書、入札関連の業務が属人化しており、紙やExcelを使って管理しているケースが少なくありません。
Salesforceでは、見積作成から契約締結、入札結果の記録までをデジタルで一元管理できます。過去の見積テンプレートを再利用したり、類似案件との比較検討を行ったりすることで、作業の精度とスピードが大きく向上します。
また、各書類が紐づいた形で案件管理の中に蓄積されるため、万一のトラブル時にも迅速な対応が可能になります。
工程進捗・対応履歴のトラッキング
施工に入ってからも、案件単位での進捗確認や履歴の記録が重要です。Salesforceでは、施工開始日、中間検査、完工予定日といった工程ごとのステータスをカスタマイズして登録できます。
また、クライアントや社内からの問い合わせ履歴、追加対応の記録なども紐づけることで、「この案件はいつ、誰が、どんな対応をしてきたのか」を時系列で追えるようになります。
このように、Salesforceを導入することで現場情報と営業情報が一元的に管理され、社内の連携ロスを最小限に抑えることができます。
モバイル活用による現場との連携
建設業においては、オフィスと現場の距離があることが多く、現場担当者と営業担当者の情報連携に課題を感じる企業も少なくありません。
Salesforceはモバイル対応も充実しており、スマートフォンやタブレットからの利用が可能です。現場から直接、報告・確認・写真添付などを行えるため、移動中や作業中でもリアルタイムな情報共有が実現します。
このような環境が整えば、営業が案件の進行状況を即座に確認したり、現場スタッフが顧客情報を見ながら対応したりと、部署横断的な情報活用が促進されます。
Salesforce導入によって得られる業務改善効果
担当者依存の排除と業務標準化
建設業では「この取引先は〇〇さんしか分からない」「この案件はベテランの△△さんがいないと進められない」といった、担当者に依存した業務運営が多くの現場で課題になっています。
Salesforceを導入することで、営業・顧客対応・見積・契約などのすべてのやり取りや履歴がシステム上に記録・共有されるようになります。これにより、担当者が不在の際でも業務が止まらず、属人性の排除と業務の標準化が実現されます。
「どの案件が、どの段階にあるか」「何を誰が対応したのか」が明確になることで、業務のブラックボックス化を防ぎ、組織としての対応力が強化されます。
情報の一元管理によるタイムロス削減
建設業においては、案件に関する情報が「営業」「積算」「施工」「経理」など各部門に分散しがちです。Salesforceは、こうした情報を案件単位で一元管理することができます。
たとえば、1つの案件に対し、
- 営業が登録した商談内容
- 見積書の金額と条件
- 現場からの進捗報告
- クライアントとのやりとりの履歴
といったデータがひとつの画面で確認できるため、社内確認のためのメールや電話が激減します。
情報を探す時間・確認する時間・伝える時間のロスが減り、日常業務のスピードと正確性が大幅に向上します。
経営層の意思決定スピード向上
経営判断を行う際に必要な「受注見込み」「受注残」「粗利率」「成約率の推移」などの情報が、リアルタイムで取得できるのもSalesforceの強みです。
ダッシュボード機能を活用することで、
- どの営業がどのエリアで成果を出しているか
- 今後受注が見込まれる案件の金額規模やスケジュール
- 成約までにかかる平均日数やボトルネック
といった経営判断に必要な指標を即座に可視化することができます。
これにより、戦略的な営業計画の立案や、早期の軌道修正が可能になり、経営リスクの最小化にもつながります。
案件の受注率・利益率アップ
案件の進捗状況や過去の成功・失敗データをもとに営業戦略を練り直すことができるため、Salesforceの導入によって受注率や利益率の改善が期待できます。
たとえば、過去の失注案件に共通する条件を分析し、提案内容を調整したり、競合との違いを強調する営業資料を準備したりといった、根拠ある改善アクションが実現します。
また、粗利管理の観点でも、見積〜契約〜原価に至るまでの情報がつながっていれば、赤字リスクの高い案件を事前に把握し、受注判断に活かすことができます。
建設業におけるSalesforce導入の成功ポイント
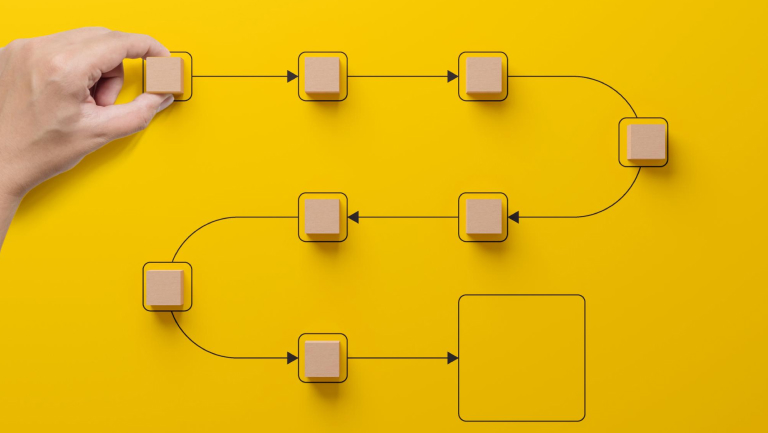
既存業務フローとのすり合わせ
Salesforceを導入する際に最も重要なのは、「今ある業務フローをどこまで変えるのか、それともどこに合わせてシステムを設計するのか」という視点です。
建設業では、長年の慣習や帳票類が根強く残っているケースも多く、いきなり全てをデジタルに置き換えると現場が混乱しかねません。まずは、現状の業務プロセスを丁寧に棚卸しした上で、Salesforceで再現可能な部分と改善すべき部分を明確に分けることが成功の第一歩です。
業務フローのすり合わせは、ITベンダーや導入支援パートナーとの連携も重要になります。無理にシステムに合わせるのではなく、「業務が回る」設計を前提とした柔軟な導入が求められます。
カスタマイズと拡張性の活用
Salesforceの大きな特長のひとつが、柔軟なカスタマイズ性と拡張性です。建設業は業態・企業規模・地域性によって必要な機能や使い方が大きく異なるため、汎用的なツールでは対応しきれないケースも多々あります。
たとえば、
- 案件管理のステータスを自社の工程管理に合わせて変更
- 顧客の属性を法人・施主・紹介会社などで分類
- 見積や契約に紐づく独自の帳票レイアウトを反映
といった要望にも、設定ベースで柔軟に対応可能です。必要に応じて、AppExchange(Salesforce公式マーケットプレイス)で業種別アプリを組み合わせることもできます。
重要なのは「業務にシステムを合わせる」視点を持ちながら、カスタマイズが過剰にならないようにするバランス感覚です。
社内浸透のためのステップと教育方法
どれだけ良いシステムを導入しても、現場に使われなければ意味がありません。Salesforceの活用を社内に浸透させるには、「最初のつまずき」を減らす工夫と、段階的な教育が欠かせません。
具体的なポイントとしては:
- 導入初期は最低限必要な機能だけに絞ってスタート
- 属人的に使うのではなく、チームで使い方の型を共有する
- マニュアルよりも、操作体験や動画マニュアルが有効
- 成功している社員の活用事例を社内で発表・共有する
こうした仕掛けを通じて、「Salesforceを使えばラクになる」と実感してもらうプロセスを大切にする必要があります。
中小規模建設業でも始められるスモールスタート
Salesforceというと「大企業向け」「費用が高い」といった印象を持たれがちですが、実際には小規模な建設会社でも段階的に導入することが可能です。
たとえば、
- まずは顧客管理だけをSalesforceで運用し、他は従来どおり
- 使いながら徐々に見積・契約・進捗などに範囲を広げていく
- 将来的に必要になった段階で、他のシステムと連携させる
といったスモールスタート+スケーラブルな設計ができるのが、Salesforceの大きな魅力です。
「最初からすべてを完璧にやろうとせず、まず1つ業務改善の成果を出すこと」が、中小建設業にとって現実的なアプローチと言えるでしょう。
よくある失敗例とその回避策
Salesforceは建設業にとって非常に有効なツールですが、「導入すればうまくいく」というものではありません。実際には、初期の設計ミスや社内の理解不足によって、期待した効果が得られないケースもあります。ここでは、建設業におけるSalesforce導入時の典型的な失敗パターンと、それを避けるための具体策を解説します。
機能過多による混乱
あれもこれも一気にやろうとして、結果的に使いこなせない。これは非常に多い失敗例です。Salesforceは非常に高機能で拡張性のあるプラットフォームですが、初期段階からすべての機能を実装しようとすると、現場は混乱します。
とくに建設業では、紙やExcelからの移行となるケースも多いため、最初は「顧客管理」「案件管理」など最も効果が出やすい領域に絞って導入することが大切です。その後、現場や営業部門での定着状況を見ながら、段階的に機能を拡張していくアプローチが現実的です。
現場と管理部門の視点ギャップ
IT導入はつい「管理部門視点」になりがちですが、実際に使うのは現場の担当者です。管理部門が「これで便利になる」と思って作った仕組みが、現場では「入力が手間」「操作が複雑」と捉えられ、定着しないことも少なくありません。
このギャップを埋めるためには、導入設計の段階から現場の声を反映させることが不可欠です。導入後も、「使いにくさ」「運用上のひっかかり」があれば、こまめにフィードバックを収集して改善していく姿勢が求められます。
目的不明瞭な導入による形骸化
「とりあえずDXの流れに乗って導入したが、何を目指しているのかが曖昧」
このようなケースでは、導入しても結局現場に定着せず、「結局、Excelに戻っている」という状況に陥りがちです。
Salesforceを導入する際には、
- どの業務をどれだけ効率化するのか
- 誰が、どんな目的で使うのか
- 導入後の指標(入力率、対応スピード、成約率など)
といった目的と効果測定の軸を最初に明確にしておくことが重要です。導入の意義が社内で共有されていれば、「何のために使うのか」が現場にも伝わりやすくなります。
ツール任せで終わるなんちゃってDXのリスク
システムを導入しただけで「DX化した」と考えるのは危険です。本質は「業務のあり方を見直すこと」にあります。
たとえば、Salesforceを入れたのに、案件の進捗管理は紙の工程表のまま。現場の声は口頭で伝える習慣が残り、システムには何も記録されない。このような状況では、いくらツールが優れていても効果は出ません。
DXの成功は「仕組み」と「習慣」の両輪で成り立っています。Salesforceを起点に、業務プロセスや社内文化を少しずつ変えていくことが、持続的な成果につながる鍵です。
まとめ:建設業におけるDXの第一歩としてのSalesforce活用

建設業界が直面する人手不足や高齢化、業務の属人化といった課題に対して、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が注目されるようになってきました。しかし、DXは決して大規模な投資や難解な技術から始まるものではありません。まずは「日々の業務における情報の流れを整えること」、そして「人に依存しない仕組みづくり」から始めることが重要です。
DXを現実に変える実務ツールとしての価値
Salesforceは、顧客情報や案件進捗を一元管理できるだけでなく、部門を横断した情報共有や営業活動の見える化、そして経営判断に必要なデータの可視化を可能にします。つまり、「現場の感覚」や「個人の記憶」に頼っていた情報管理を、組織の資産に変えるツールです。
建設業においては、営業、見積、契約、施工、アフター対応といった一連の流れが各担当者に分断されていることが多く、そこに起因するミスやロスが数多く存在します。Salesforceを活用することで、点在していた情報を一本の線に繋げることができるのです。
まずは「情報がつながる仕組み」から始めよう
DXという言葉にとらわれる必要はありません。まずは「誰が、いつ、どの案件に、どのように関わっているのか」がリアルタイムで把握できる環境を整えること。それが業務効率化への第一歩であり、ひいては企業の競争力につながります。
Salesforceは高機能であるがゆえに、使い方を誤ると宝の持ち腐れになることもありますが、逆に言えば現場の課題に応じて最適化できる柔軟性があるとも言えます。カスタマイズ次第で、大企業だけでなく中小規模の建設業でも十分に効果を発揮します。
情報の流れが整理されれば、余計な確認作業や手戻りが減り、本来注力すべき「安全」「品質」「納期」などの本業に集中できる環境が整います。これは現場で働く一人ひとりのストレスを減らし、生産性向上や離職防止にもつながっていくはずです。
現場業務と情報をつなぐアプリ「現場へGO!」とは?
SalesforceのようなCRMを活用しても、どうしても「現場の情報」は取りこぼされがちです。たとえば、日報の記録や現場写真の共有、作業進捗のリアルタイムな把握といった領域は、Excelや紙の書類、LINEなどのチャットアプリで管理されていることが少なくありません。
こうした現場業務の情報の断絶を補完するのが、「Salesforceプラットフォーム上で動く建設業向けアプリ現場へGO!」です。
Salesforceと連携し、現場の情報も一元管理
「現場へGO!」は、Salesforceのクラウド基盤を活用して開発された現場管理に特化した業務アプリケーションです。現場の作業員や協力会社がスマートフォンやタブレットから日報を記入し、写真をアップロードし、進捗をリアルタイムで報告することができます。
Salesforceと連携することで、営業・案件情報と現場情報が1つのデータベースに統合され、二重入力や確認作業が大幅に削減されます。経営層、営業担当者、現場監督、それぞれが必要な情報を即時に把握できるようになります。
現場にもやさしい操作性と柔軟なカスタマイズ性
現場へGO!の特長は、「現場で使えること」を前提に設計されている点です。スマートフォンでも快適に操作できるUI、オフラインでも一部入力が可能な仕様、写真付きで視覚的に状況を記録できる機能など、現場作業員の声を反映した機能が多数搭載されています。
さらに、Salesforceの特性を活かし、自社の業務フローに合わせた柔軟なカスタマイズも可能です。定型業務の自動化や通知機能なども活用でき、業務の属人化を防ぎつつ、ミスの削減にもつながります。
小規模現場からでも始められるDX支援ツール
DXというと大規模投資をイメージしがちですが、現場へGO!は中小規模の建設会社でも導入しやすいよう設計されています。Salesforce導入済みの企業であれば、既存の環境と連携してすぐに使い始めることも可能です。