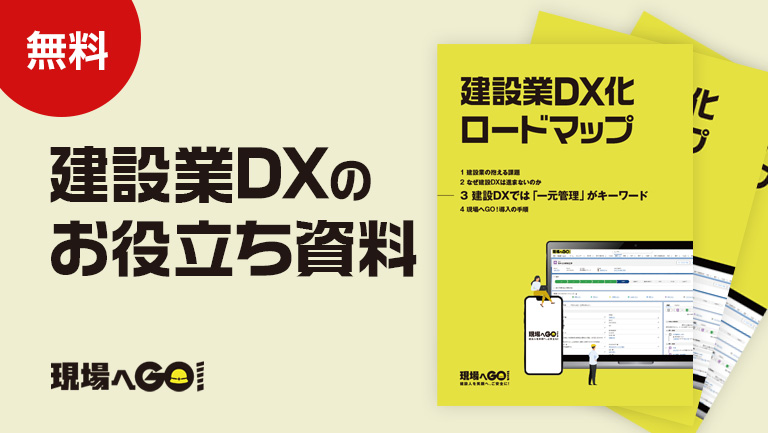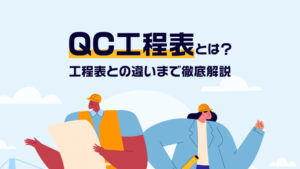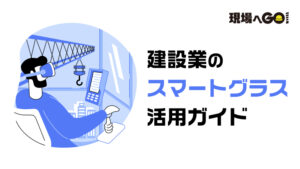【建設業向け】積算とは?見積もりとの違い・部掛(ぶがかり)の計算方法も解説!

積算(せきさん)とは?

建設現場で欠かせない「積算(せきさん)」とは、工事を行う上で必要となる材料費や人件費など、すべてのコストを事前に算出する作業のことです。簡単に言えば、「工事にいくらかかるのか?」を正確に把握するための計算であり、見積もりを作成するためのベースとなる重要な工程です。
ただし、積算で出した金額はそのまま見積書には載りません。積算はあくまで社内で把握するための原価計算であり、そこに利益や値引きなどを加味したものが、顧客に提示する「見積もり」です。
積算をしっかり行うことで、赤字工事を防ぎ、利益を確保しやすくなります。部掛(ぶがかり)と呼ばれる経費の振り分けも積算の中で大切な要素であり、実際のコスト管理に直結します。
積算の目的
利益の確保
積算の主な目的の一つは「利益の確保」です。正確な積算を行うことで、工事に必要なすべてのコスト(材料費、労務費、外注費など)を正確に把握することができます。この段階で適切な利益率を設定することで、工事の採算を確保し、企業の利益を守ることができます。利益を過大に設定したり、逆に過小に設定したりすると、最終的に赤字になるリスクがあります。そのため、積算における正確性とバランスが重要です。
正確な工事予算の把握
積算を行うことで、「正確な工事予算の把握」が可能になります。工事を始める前に、必要な材料や労務、外注費などすべてのコストを洗い出すことができます。この正確な予算の把握は、工事の進行中における費用超過を防ぐために欠かせません。適切な予算設定ができていれば、計画的な工事運営ができ、予想外の費用が発生した場合にも柔軟に対応できる準備が整います。
顧客との信頼構築
積算は「顧客との信頼構築」にも大いに役立ちます。積算を基にした見積もりが明確で透明性がある場合、顧客はその工事に対して安心感を抱きます。顧客に対して適切で正確な見積もりを提示することは、信頼関係を築く上で非常に重要です。反対に、積算が不正確であったり、不透明な価格設定が行われていると、顧客の信頼を失う原因となり、次回の取引に影響を及ぼす可能性があります。したがって、積算の段階から信頼を築くことが重要です。
経営戦略の判断材料
積算は「経営戦略の判断材料」としても非常に重要です。企業は積算によって得られたコストデータをもとに、どの工事にどれだけのリソースを割くか、利益率をどう設定するかなど、経営方針を決定します。また、積算結果を参考にすることで、事業の方向性を決めるための重要なデータとして活用することができます。工事の規模や種類に応じて適切な予算配分を行うことで、長期的に安定した経営が可能となります。
積算の主な内容・内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 材料費 | 購入する建材や部材の費用。例えば、コンクリート、鉄筋、木材など、工事に必要なすべての材料費が含まれます。 |
| 労務費 | 作業員の人件費。直営の作業員と外注業者の人件費が含まれます。人数や作業時間をもとに計算されます。 |
| 外注費 | 下請け業者への発注費用。例えば、電気工事、配管工事など専門的な工事を外注する場合の費用が含まれます。 |
| 諸経費 | 共通仮設費、現場管理費、事務所や設備のレンタル費用など、現場運営にかかるその他の費用です。 |
| 部掛 | 共通仮設費や現場管理費など、工事全体に共通する費用。現場の設営費や安全対策費用も含まれます。 |
| 予備費 | 万が一の予測外の費用に備えて、余裕を持たせるために計上される費用です。通常は全体費用の5〜10%程度。 |
| 利益 | 工事に対して設定された利益率を加算する部分。積算で計算された原価に利益を上乗せして最終的な価格を設定します。 |
部掛(ぶがかり)とは?
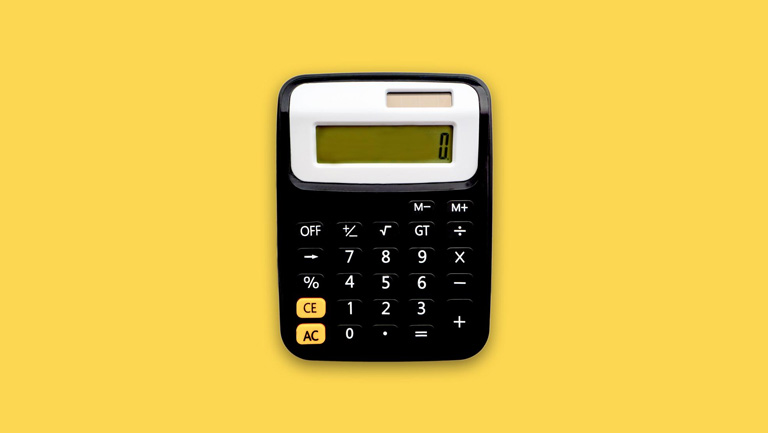
積算業務の中でも、特に見落とされがちでありながら重要な考え方が「部掛(ぶがかり)」です。建設業においては、材料費や労務費といった直接費だけでなく、現場の運営にかかる間接費も正確に見積もる必要があります。部掛は、その間接費を合理的に配分し、工事全体のコスト構造をより現実的に把握するための仕組みです。
間接費ってどんな費用?
間接費とは、例えば以下のようなコストを指します:
- 現場監督の人件費
- 仮設トイレや現場事務所などの共通仮設費
- 現場の安全管理費
- 電気・水道などの仮設設備費
これらは工事全体に関わる費用であり、どの作業項目に直接紐づくものではありません。だからといって無視できるものではなく、むしろ現場運営に欠かせないコストです。
部掛はどうやって使う?
部掛とは、これらの間接費を、直接費に対して一定の率で按分(あんぶん)する手法です。たとえば「労務費の○%」「材料費の○%」といった形で計算され、項目ごとに反映されます。
これは一律の経費率を適用することで、工事ごとの実態に即した見積もりが可能になり、工事全体のコスト感を見誤ることを防ぎます。
なぜ部掛が重要なのか?
仮に部掛を正しく行わなかった場合、間接費が過少に見積もられてしまい、利益を圧迫したり、後から追加請求が発生したりといったリスクがあります。逆に部掛をしっかりと反映させておけば、正確な予算管理ができるだけでなく、現場運営に必要なコストを最初から見積もりに組み込めるため、顧客との信頼関係構築にもつながります。
積算と見積もりの違いとは?
「積算」と「見積もり」は似ているようで、実は異なる役割を持っています。
| 比較項目 | 積算 | 見積もり |
|---|---|---|
| 目的 | 原価を正確に把握する | 顧客に価格を提示する |
| 視点 | 内部コスト計算 | 顧客への提案 |
| 利益 | 含まれていない | 含まれている |
| 使用場面 | 社内資料や工事計画 | 顧客への営業活動 |
積算は工事に必要な経費を洗い出す工程であり、見積もりは積算に加え「利益」や「値引き」などを加味して提示する「価格設定」です。両方がしっかり連携していなければ、採算の合わない工事を引き受けてしまうリスクが高まります。
積算とは「コストの洗い出し」
積算とは、建設工事を実施するために必要なコストを細かく計算・算出する工程です。設計図面や仕様書をもとに、必要な資材や人員の量を拾い出し、それに基づいて材料費・労務費・外注費・諸経費などを積み上げていきます。
つまり積算は、「この工事にはいくらかかるのか?」という原価を明らかにするプロセス。これはあくまで施工者側の視点で行う、内向きの計算作業です。
正確な積算ができなければ、工事に必要な資源の確保もスケジューリングもずれてしまい、最終的には赤字やトラブルの原因になりかねません。
見積もりとは「価格の提示」
一方の見積もりは、積算で算出された原価に対して、利益、リスクヘッジ、場合によっては値引き要素などを加味し、顧客に提示する「販売価格」を設定する工程です。
顧客との契約金額としての「提示価格」となるため、単純なコストの合計ではなく、会社としての経営判断や営業戦略が反映されるのが特徴です。競合との価格競争や、顧客との信頼関係、案件の重要性などを踏まえて、慎重に価格を決定します。
なぜ両者の違いを理解することが重要なのか?
積算が甘ければ、正確な見積もりはできません。
逆に、積算がしっかりできていても、それを踏まえた見積もりが戦略的に練られていなければ、受注にはつながらない可能性もあります。
また、両者を混同してしまうと、「とりあえずこのくらいで」と感覚的に価格を決めてしまい、工事が始まってから「思ったよりコストがかかった」と後悔することになります。
見積もりは顧客との約束、積算は現場を支える根拠。この2つの関係をしっかり理解して連携させることが、利益を確保しつつ、顧客満足度も高めるためのカギになります。
積算の作成方法と基本手順

積算は、以下のステップで行われます。
【ステップ1】図面・仕様書の確認
まずは設計図や仕様書をもとに、どんな工事が必要かを読み取ります。必要な材料や工法を理解することが、正確な数量拾いにつながります。
【ステップ2】数量拾い
図面を見ながら、コンクリート、鉄筋、木材など、使う材料の量を一つずつ数えていきます。これを「数量拾い」と呼びます。ここでのミスは後工程に響くため、慎重な作業が求められます。
【ステップ3】単価の設定と部掛の反映
数量に単価を掛けて材料費・労務費などを計算します。この時点で、部掛(ぶがかり)と呼ばれる共通仮設費や現場管理費などの経費も加味します。これらは会社ごとのルールや実績に基づいて設定します。
【ステップ4】原価+利益=見積もり金額へ
最後に、計算した原価に適正な利益率を上乗せすることで、顧客に提示する見積もり金額が完成します。
積算でよくあるミスと注意点
積算には細かい作業が多く、注意すべきポイントもたくさんあります。以下に代表的なミスとその対策をまとめました。
| よくあるミス | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 数量の拾い漏れ | 図面の見落としや読み違い | 二重チェック・ピアレビューの実施 |
| 単価の設定ミス | 古い価格データを使用 | 定期的な単価データの更新 |
| 諸経費の計上漏れ | 小規模な費用の見逃し | テンプレートや過去実績の参照 |
| 不適切な部掛率 | 経験値不足や誤設定 | 上司・ベテランとの相談、共有ルールの整備 |
積算の精度は、工事の利益に直結します。忙しい時こそ、確認作業を怠らない姿勢が重要です。
積算に関するよくある質問

Q. 積算ソフトは導入したほうが良い?
A. はい。Excelでも対応は可能ですが、専用の積算ソフトを使うことで、作業効率や精度が格段に上がります。特に物件数が多い企業や、複雑な工種を扱う場合には導入を検討する価値があります。
Q. 小規模工事でも積算は必要?
A. 必要です。利益率の低い小規模工事では、原価管理の重要性が高くなります。少額のズレが、利益を大きく左右するため、積算の基本を怠るべきではありません。
Q. 部掛ってどうやって決めるの?
A. 一般的には、過去の実績をもとにパーセンテージを設定します。たとえば、現場管理費=直接工事費の10%、共通仮設費=5%など。経験とデータ分析が鍵になります。
Q. 積算を外注するのはアリ?
A. リソースが不足している場合は有効な手段です。外注先には信頼できる業者を選ぶ必要がありますが、社内負荷を軽減しつつ、高精度の積算結果を得ることができます。
建設業務を効率化する「現場へGO!」のご紹介
「現場へGO!」は、Salesforceのプラットフォーム上で開発された建設業向けの統合型クラウドアプリケーションです。積算業務の効率化だけでなく、現場の管理や見積もり作成、顧客対応まで、建設業に必要な業務をワンストップで支援する機能がそろっています。
階層構造の見積もり作成で業務をスピードアップ
建設業に欠かせない階層型の見積もりも、「現場へGO!」ならSalesforce上で簡単に作成可能です。テンプレートやマスタのグループ化、多彩な自動化機能によって、積算専用ソフトに匹敵するスピードと精度を実現。さらに、見積もりデータから工程表や発注書への連携もスムーズに行えます。
グラフィカルな工程表で現場の進捗を見える化
属人化しがちな工程管理も、「現場へGO!」ならグラフィカルなWEB工程表でわかりやすく共有。現場担当者が作成した工程表をリアルタイムで全社共有できるため、作業のズレや伝達ミスを大幅に削減できます。経験値に頼らず、誰でも工程を「見える化」できるのが大きなメリットです。
案件の最初から最後まで、すべてを一元管理
お客様との出会いから契約、施工、引き渡し、そしてアフターサービスまで。すべての情報を一気通貫で蓄積・管理できるのが「現場へGO!」の大きな特長です。現場ファイルを手元で管理する必要はもうありません。スマートフォンひとつで、現場に関するすべての情報にアクセス可能になります。
これらの機能により、現場と事務方の連携がスムーズになり、積算業務の正確性と効率が大きく向上します。積算は「利益を守るための第一歩」とも言われ、正確な積算ができれば、見積もりや工事計画も安定し、無駄な出費や赤字のリスクを回避することができます。特に利益率が限られる建設業界においては、積算の精度がそのまま会社の信頼や収益につながるのです。
日々の忙しさに追われる中でも、確認作業を怠らず、必要に応じてツールや外部サービスを活用することで、積算業務の質を高めることができます。「現場へGO!」のようなアプリケーションを導入することは、建設業の持続可能な経営に向けた大きな一歩となるでしょう。